于氏(ウ氏)王后は彼女は高句麗の9代・故国川王と10代・山上王、二人の王の妃。二度王妃となった人物です。
夫の死を隠して弟王を立てたと伝えられます。その行動は裏切りか、それとも国を守る政治的決断だったのか?時代を超えて語り継がれるこの王妃の真実に迫ります。
【この記事でわかること】
- 于氏(ウ氏)王后の出自と高句麗五部体制における地位
- 王の死を秘し弟を王に立てた背景と意味
- 「娶嫂婚(レビラト婚)」という当時の婚姻制度
- 儒教・フェミニズム・外戚政治の各史観による評価
- ドラマ『ウ氏王后』が描く現代的解釈
于氏(ウ氏)王后とは?
高句麗の王妃・于氏(うし/ウ氏)王后は第9代・故国川王と第10代・山上王の王妃になった人物です。彼女の素性と当時の高句麗の社会のしくみから紹介します。
出身部族は椽那部
于氏(ウ氏)王后は高句麗の有力部族・椽那部(ヨンナブ)の出身とされます。三國志では絶奴部と書かれている部族。
当時の高句麗は五部体制を敷き、王家(桂婁部)と各部族が婚姻で結びついていました。椽那部は王家の次に力のある部族で、代々王妃を出す家柄でした。
絶奴部(提那部/椽那部)とは
- 行政的には「北部」「後部」「黒部」とも呼ばれる。
- 王族桂婁部(ケルルブ)に次ぐ第二勢力の部族。
- 王妃・王族の婚姻相手を多く出し、王家と外戚関係を維持した。
- 王妃が代々この絶奴部から出ることが多く、王家に準ずる待遇を受けていた。
- 部族の起源は扶余(プヨ)系統と考えられ、文化的にも北方騎馬民族の性格を残していた。
于氏(ウ氏)王后は族長の娘だった
于氏(ウ氏)王后の父は椽那部の族長・于素。
-
9代 故国川王の正妃
二人の間に子はいません。 -
10代 山上王=弟王の王妃
故国川王の死後、山上王となった弟と再婚。 -
11代 東川王の代まで太后として存命
このため、彼女は2回王妃になった珍しい王妃です。
『三國史記』に見る于氏王后の行動
于氏王后の記録は少ないです。限られた史料から王の死後、彼女がどのように行動したのか紹介します。
王の死を隠し、夫の弟を王に立てる
「王后于氏,秘不發喪,夜往王弟發歧宅,曰:王無後,子宜嗣之。」
『三國史記』巻16「山上王」
王妃は王の死を隠したまま、夜中に王弟・発岐(のちの山上王)の家を訪れ「王には跡継ぎがいません。あなたが継ぐべきです」と言った。
と記録されています。つまり、王位継承に関わった人物として描かれているのです。
山上王の即位と于氏の地位
「王本因于氏得位,不復更娶,立于氏為后。」
『三國史記』巻16「山上王」
山上王は于氏を得て即位。二度と妻を娶らず、于氏を王妃とした。
このことから、于氏の存在が新王の即位を支えた要因だったとわかります。
晩年の懺悔 ― 儒教的断罪
「太后于氏薨。臨終遺言曰:妾失行,將何面目見國壤於地下?」
『三國史記』巻17「東川王条」
太后 于氏が崩御。臨終の際、彼女は次のような遺言を残しました。「私は行いを誤ってしまいました。どのような顔をして地下で国王様にお会いすればよいのでしょうか。」
于氏は死の間際に夫の弟と再婚したことを恥じたといいます。
確かに現代人の感覚からすれば夫の弟と結婚するのは不自然です。
でも北方の遊牧民の間ではこのような結婚(レビラト婚)はありますし。どこまで彼女の言葉かはわかりません。
あるいは高麗時代の儒教的価値観に基づき、女性が再婚したことや、政治に関わったことを不道徳な行いとして描いたのかもしれません。
驚きの風習 :「娶嫂婚」とは?
現代人からみれば、「夫が亡くなったあと、その弟と再婚する」というのは驚くかもしれません。
でも北方民族や古代の東アジア、特に高句麗ではそういう慣習がありました。それが「娶嫂婚(チィスホン)」、いわゆるレビラト婚(Levirate marriage)です。
制度の目的は血統と家門の維持
娶嫂婚とは兄が亡くなったあと弟が兄の妻(嫂)を娶る婚姻制度。
現代的にはおかしな制度に見えますが、当時の社会では非常に合理的な仕組みでした。
目的は三つあります。
- 血統の断絶を防ぐ
夫が子を残さず死んだ場合、弟が嫂を娶って跡継ぎをもうける。 - 財産・領地の流出を防ぐ
婚姻を通じて動いた財産を外部の部族に移さない。 - 同盟関係(外戚政治)の維持
王妃が外部の有力部族出身だった場合、再婚によって政治同盟を継続する。
つまり、娶嫂婚は「家を守るための再婚」であって、個人の愛情よりも「血統と秩序の維持」が優先された制度でした。
史料に見る娶嫂婚 :『三國志』の記録
『三國志・魏志東夷伝 高句麗条』には次のような記述があります。
「其俗兄死則娶其嫂」
つまり、「兄が死ねば弟がその嫂を娶る」というのが高句麗の慣習だったのです。これは古代中国の史官が“異民族の風俗”として記したもの。外国人が気がつく程度には知られていた知恵た習慣だったことがわかります。
そのため。于氏の行いは異常なことのように思えますが。当時の慣習では十分ありえることだったのです。
于氏(ウ氏)王后の歴史的な評価とは?
この于氏の行いは見る人や時代によって様々な解釈があります。
儒教的史観:「矯命」と「失行」の倫理
『三國史記』の筆者・金富軾は典型的な儒教的道徳史観の立場に立っています。
そのため、于氏の行動は「王命を偽り」「礼を乱した」として批判的に書かれています。
「矯先王命」=王命を偽る
「妾失行」=礼に背いた女性の自責
この表現は女性が政治の中枢に入るのを「秩序の崩壊」と考える思想に基づいています。史実そのものよりも、儒教倫理を守らせるための警告的な作文といえるでしょう。
フェミニズム史観 :「王位を動かした女性」の再評価
近年、韓国では于氏を“王権を動かした女性”として再評価する傾向があります。
Sookja Cho(2014)は、「三國史記」における女性像を再分析、儒教的断罪の背後に政治的主体としての女性の実像があると主張しました。
“矯命”は裏切りではなく、国家の空白を埋める政治的行動だった。
このような視点は現代人の価値観や願望が入ってます。フェミニズム運動を歴史の解釈に当てはめたもの。
でも当時の外戚同盟や部族政治といった社会の様子を無視している。史実の再解釈としては客観性に劣るといえます。
外戚政治としての王位継承:于氏の役割
思想的な感想ではなく、歴史の資料からわかる事実はどうだったのでしょうか?
『三國史記』故国川王条にはこうあります。
「皆以王后親戚,執國權柄。」
『三國史記』故国川王
すべて王后の親族が国政を握った
『三國史記』の記録が意味するのは王妃本人よりも外戚一族による集団支配です。于氏は王家と有力部族を結ぶ婚姻同盟の象徴として、王権の連続性を保つために動いたと考えられます。
もともと椽那部は五部の中でも王家に継いで力のある部族で、王妃を送り出すことで政治的な発言力を維持してきました。
王妃個人の問題というより、一族の都合なのです。
これは漢の竇太后、王政君、日本の蘇我氏、百済の沙宅氏と同じ。高句麗での外戚政治の代表的な例といえます。
ドラマ『ウ氏王后』とは: フュージョン時代劇としての再解釈
史実をモチーフにした新解釈ドラマ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | 『ウ氏王后(우씨왕후)』 |
| 配信 | TVING(2024年8月〜9月) |
| 主演 | チョン・ジョンソ、キム・ムヨル、イ・スヒョク |
| 形式 | フュージョン史劇(퓨전 사극)/全8話 |
| ジャンル | アクション × 政治劇 × サスペンス |
ドラマは史実を直接再現するのではなく、
古代高句麗を舞台にした創作的再構成として作られています。
王妃ウ・ヒは、王の死後「24時間以内に弟王子と娶嫂婚する」ことで生き残りを賭けるヒロイン。
王子たち・部族たちの争いの中で、自ら運命を切り拓く物語が展開されます。
ドラマのあらすじ(概要)
王・コ・ナンムが急死。子のない王妃ウ・ヒは、一族もろとも宮廷から追放される危機に立たされます。
唯一の生き残る道は、24時間以内に弟王子の一人を王に立て、自らその妃となること。
裏切り・暗殺・五部族の抗争の中で、ウ・ヒは自らの意志で政治を動かし、最終話では再び王妃として即位、物語を締めくくります。
史実との違い ― 「懺悔の死」→「生存と自立」へ
| 観点 | 史実 | ドラマ |
|---|---|---|
| 主題 | 道徳的戒め(儒教史観) | 生存と自立(現代的フェミニズム) |
| 結末 | 懺悔して死去 | 再び王妃となり生き延びる |
| 王妃像 | 外戚政治の調整者 | 戦うヒロイン |
| 婚姻 | 政治的再婚 | 愛と同盟の象徴 |
TVING側も制作発表で「史実にこだわらない、新感覚のアクション・サスペンス」と発表しています。このドラマは史実の再現ではなく、“現代的メッセージを含んだ作り話”として制作されています。
まとめ: 三つの「ウ氏王后」像
| 視点 | 特徴 | 評価軸 |
|---|---|---|
| 儒教史観 | 不義の王妃 | 道徳的批判 |
| フェミニズム史観 | 権力を動かした女性 | 自立と主体性 |
| 史料からわかる事実 | 部族同盟の要 | 政治的調整者 |
于氏王后は“野心で歴史を変えた女傑”でも“悲劇の妃”でもなく、外戚政治の一員。外戚の立場から王位継承に介入、一族と自分のために行動した人物といえそうです。
ドラマ『ウ氏王后』はフュージョン時代劇として現代的な感覚で脚色。「女性が歴史を作る」物語として描き直した作品です。
参考文献
-
『三國史記』巻16〜17(高句麗本紀)
-
尹淑熙「高句麗の王位継承と外戚の影響」(『韓国古代史論叢』第18号, 2004)
-
Cho, Sookja. “Gender Equality and the Practice of Virtue in the Samguk sagi.” Korean Studies, 2014.
-
Chung Hyun-Back (ed.), A History of Korean Women, 2021.
-
金貞培『高句麗政治史研究』(延世大学出版部, 1992)
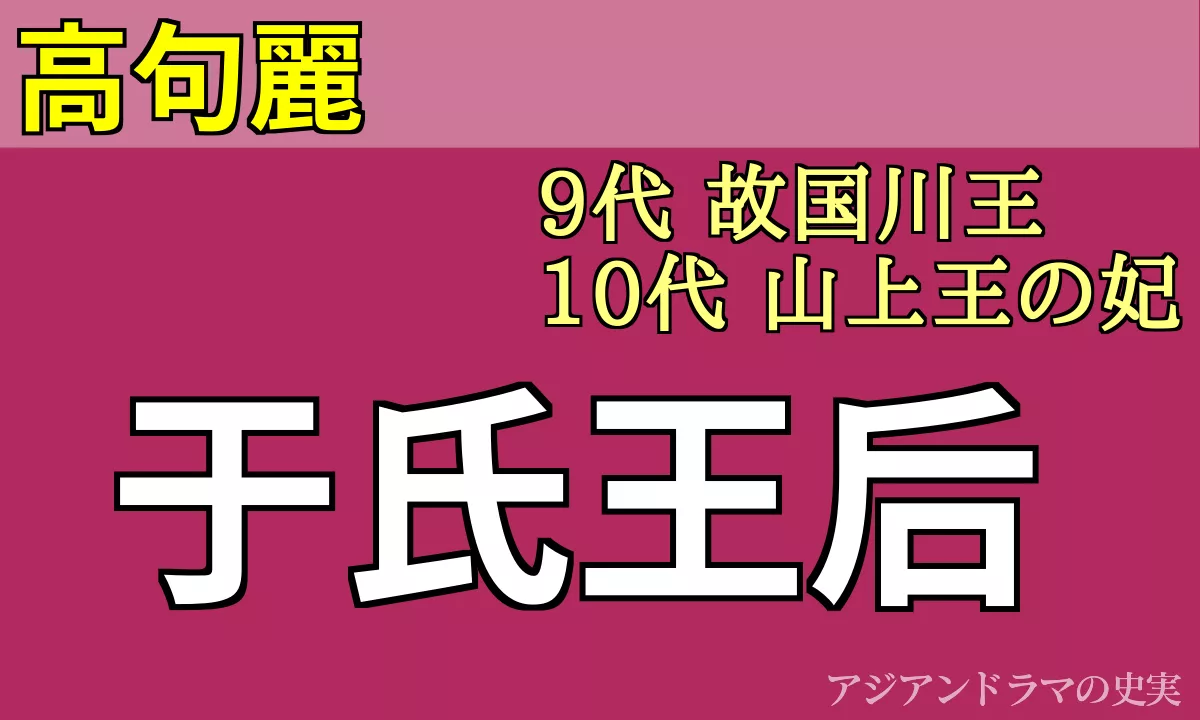

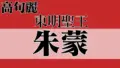

コメント