高句麗は中国東北部と朝鮮半島北部に成立した王国。ドラマ『朱蒙(チュモン)』『風の国』『太王四神記』では、強大な騎馬軍団を率いる勇猛な王国として描かれますが、「実際の高句麗はどんな国だったのか?」と聞かれると、意外とはっきり説明しにくいかもしれません。
高句麗は山あいの小さな勢力から始まり漢・隋・唐といった大国と渡り合う軍事大国へと成長。数百年にわたって存在しました。
この記事では「高句麗とはどんな国だったのか?」を軸に建国神話としての朱蒙伝説から、実際の歴史、滅亡後に残された遺産までわかりやすすく紹介します。
この記事で分かること
- 高句麗の成り立ちと、扶余伝承・漢の行政制度との関係
- 初期の地理的中心、勢力拡大の過程、平壌移動の背景
- 農耕・狩猟・騎馬文化が混在する生活と、漢文化との共存構造
- ドラマ作品との違いから見える史実の高句麗像と滅亡の要因
高句麗とは?
高句麗(こうくり)は、紀元前1世紀ごろから7世紀まで、いまの中国東北部(吉林・遼寧あたり)と朝鮮半島北部にまたがっていた王国です。
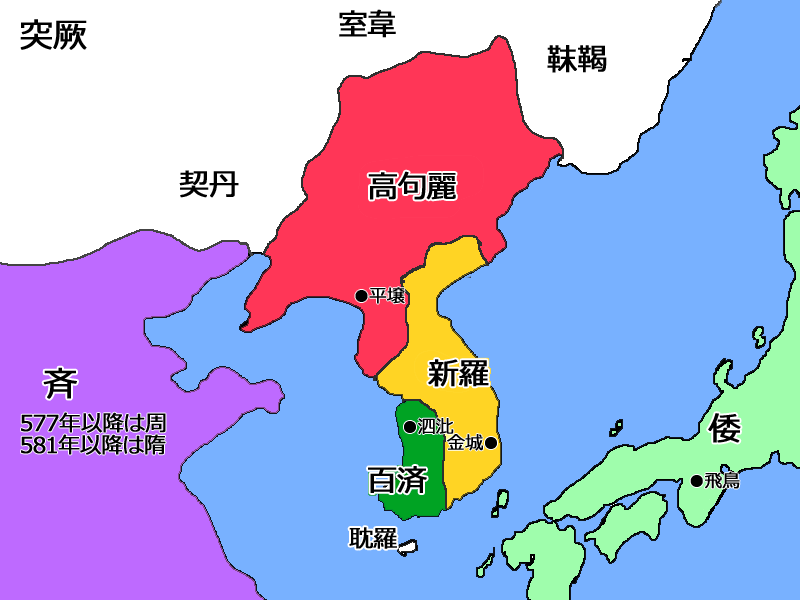
6世紀ごろの高句麗
山や川の多い土地で、農耕・狩猟・一部の牧畜を組み合わせて暮らしていた人びとが、漢字文化や官職制度を取り入れながら独自の国家を育てていきました。
ドラマ『朱蒙(チュモン)』『風の国』は、この高句麗の建国伝承や王族の争いを題材にした作り話で、史実とは違います。
高句麗の成り立ちと伝承
史料に見える高句麗のはじまり
高句麗は中国の史書や『三国史記』などに書かれています。紀元前1世紀ごろ、いまの吉林省から遼寧省北部あたりに城を構えて活動していた集団として登場します。
そこでは
- 山や川に囲まれた土地に山城や平地城を築き
- 周囲の集団を従えながら少しずつ勢力を広げていく、
といった姿がうかがえます。
この段階の高句麗は、まだ「東アジアの大国」というほどではなく、北東アジアの一角で力をつけていく地方政権という印象が近いかもしれません。
朱蒙伝承とはどんな物語か
朝鮮側の史書である『三国史記』や『三国遺事』には高句麗の始祖として朱蒙(チュモン)の物語が語られています。
そこにかかれているのは
-
父は天帝の息子・解慕漱
-
母は水神河伯の娘・柳花
-
卵から生まれ、弓の名手として成長
-
嫉妬や迫害を受け、新しい国を築くために旅立
という典型的な英雄物語です。
ここで知っておきたいのは
-
朱蒙伝説には「古朝鮮」は登場しない、
-
「衛氏朝鮮」や「平壌」といった国や地名も登場しないこと。
ドラマ『朱蒙』では
-
古朝鮮の滅亡
-
漢の支配
-
その中で立ち上がる朱蒙
といった流れが強調され「古朝鮮→朱蒙→高句麗」という一本の歴史物語のように描かれますが、これはあくまで創作です。
史書に残る朱蒙伝説は 扶余の国内で起きた権力争いからの脱出と建国の物語であり、古朝鮮は関係ありません。
扶余と高句麗の関係は?
朱蒙の物語の舞台になる「扶余(夫余)」は、現在の中国東北部・松花江流域あたりにあったとされる国です。高句麗の建国伝承では
-
朱蒙は扶余の王家または有力者の子
-
扶余を離れて新しい地で高句麗をつくった
というストーリーになっています。
さらに注意したいのは
-
扶余の中心地とされる場所は古朝鮮があったとされる平壌からかなり遠いこと、
-
初期高句麗の拠点も吉林・遼寧北部あたりで、こちらも平壌から大きく離れていること、
この2点は押さえておきたいところです。
つまり、
古朝鮮(平壌周辺) → 扶余 → 高句麗
という一本の流れを描くのは、ドラマ『朱蒙』の演出であり、史実ではありません。
高句麗と扶余の関係については。何らかの系譜や文化のつながりを感じさせる伝承がある一方で、それがどこまで繋がっているかは、はっきりわからないのです。
史実としての高句麗の始まり:漢の属領・高句驪県
では、神話ではなく歴史書の中での高句麗の最初の登場はどうなっているのでしょうか。
中国側の史書によると、紀元前107年。
前漢は現在の遼寧北部付近に「玄菟郡(げんとぐん)」を設置し、その配下の県のひとつとして「高句驪県」を置きました。これが高句麗という名前が史料に現れる最初の例です。
位置関係はだいたい以下の通りです。
図の衛氏朝鮮が「古朝鮮」と言われる国。漢は紀元前108年に衛氏朝鮮を滅ぼして楽浪郡を設置しました。ドラマ『朱蒙』では古朝鮮は満洲地方や北京まで含めたかなり広く描かれていますが、実際にはこの図の大きさだったと考えられています。

漢四郡が設置された頃の朝鮮半島の地図
高句麗があったのは楽浪郡から離れた玄菟郡の周辺。玄菟郡も濊貊など地元勢力を抑えるために漢が設置した行政単位。
当時の高句驪県は
- 玄菟郡の下に置かれた一つの県
- 周辺の部族や集団を管理するための行政単位
という扱いで、高句麗はまだ漢の支配下の一地域にすぎませんでした。
高句麗侯への昇格:直接支配から冊封へ
状況が変わるのは紀元前75年ごろのことです。前漢は玄菟郡を西へ移し、新しい玄菟郡をつくりました。
その際、もともと高句驪県のあたりにいた集団の首長に漢は「高句麗侯」という爵位を与えています。
つまり。
-
それまでの「県」としての直接支配をやめ、
-
現地の首長に「侯」の称号を与えて間接支配(冊封)に切り替えた、
ということです。
こうして、漢の行政単位だった「高句驪県」 → 現地首長が治める「高句麗侯の領域」
と変化して、この地域がのちの高句麗王国の核へと育っていったと考えられます。
また時期ははっきりしませんが、前漢のあいだに高句麗侯が「王」へ昇格した可能性や、漢からの称号とは別に内部ではもっと早くから自らを「王」と称していた可能性もあります。
外向きの爵位と集団の内部で使われる称号が一致しないのはよくあることで、表向きは「侯」でも身内では「王」と名乗るといったことも十分ありえます。
というわけで
-
初めは漢の属領として登場
-
しだいに自律性を強め
-
地域の有力政権へと姿を変えていく
という流れが史料から分かる高句麗の出発点になります。
高句麗はどこにあった?地理と勢力範囲
初期高句麗:吉林・遼寧北部に重心
初期の高句麗はいまの中国・吉林省から遼寧省北部にかけての地域を中心にしていました。
とくに鴨緑江(現在の北朝鮮と中国の国境となっている川)の上流域にある集安周辺は古い都の候補地としてよく名前が挙がります。
このあたりは
-
川沿いに比較的開けた土地がある
-
そのまわりを丘陵や山地が取り囲む
という地形をしています。
高句麗の人びとは川沿いの土地で耕作を行い、山や丘陵には城を築き。周囲の集団を取り込みながら、少しずつ勢力を固めていきました。
ドラマでは韓国国内の山地ロケが多いため「山奥にある国」という印象になりがちですが、史料や遺跡の位置から見ると、初期高句麗の重心はむしろ満洲寄りの川沿いの世界にあったと考える方が自然です。
拡大期:東北アジアの有力政権へ
時代が下るにつれ、高句麗は周囲のさまざまな集団を従えながら勢力を広げていきます。
とくに4~5世紀の広開土王や長寿王の時代には、
-
中国東北部のかなり広い範囲(遼寧省・吉林省・黒龍江省)
-
朝鮮半島北部から中部にかけての地域
にまで軍事的・政治的な影響力を及ぼしていたと考えられています。
この頃の高句麗は
-
中国大陸側の政権(魏・晋・隋・唐など)
-
朝鮮半島の百済・新羅、
と絶えず戦いや交渉をくり返す立場にありました。
ただし当時の「領土」を現代の地図のように明確な国境線で区切ることはできません。
-
直接支配していた「核となる地域」、
-
周辺の勢力が服属したり離反したりする「ゆるやかな勢力圏」、
これらが重なりながら広がっていた、と考える方が史実に近いでしょう。
平壌との関係:古朝鮮との連続性に注意
5世紀の長寿王の時代に高句麗は都を平壌方面へ移したといわれています。
そのため、
-
古朝鮮(衛氏朝鮮)の中心が平壌周辺
-
高句麗後期の都も平壌付近
という地理的な重なりが生まれます。
この並びだけを見ると、「古朝鮮のあとに、そのまま高句麗が入れ替わった」という一本の連続した流れを想像したくなりますが、ここは注意が必要です。
というのも、
-
初期高句麗や扶余の中心地は、もっと北東寄り(吉林・遼寧北部)にあった
-
古朝鮮の領域や性格そのものにも不明な点が多い
という事情があるからです。
つまり、
ドラマを見てると錯覚しがちですが。現実は違うというのを覚えておきましょう。
高句麗をつくった人びとと生活
濊・貊など在地集団と高句麗
中国の史書には東北アジアの住民として「濊(わい)」「貊(はく)」と呼ばれる人びとが登場します。
これは、
-
いまの吉林・遼寧北部
-
朝鮮半島北部
このあたりで暮らしていたさまざまな集団をまとめて指す呼び名だと考えられています。
彼らの生活は
-
山や森の多い土地での狩猟
-
畑を開いての雑穀栽培
-
場所によっては馬や家畜の飼育
こうした活動を組み合わせて暮らしていたようです。
高句麗はこのような在地の人びとを土台にしつつ、扶余をはじめ周囲の諸集団や漢の支配下にいた人びとなどを取り込みながら出来上がった国だった、といえるかもしれません。
そのため高句麗は
農耕・狩猟・牧畜を組み合わせた生活
高句麗の人びとの暮らしは、一言でまとめると「農耕+狩猟+一部の牧畜」を組み合わせた生活でした。
具体的には
-
川沿いの平地や谷あいで雑穀などを育て
-
山や森で狩りや木の実採集を行い
-
地域によっては馬や家畜も飼いながら
それぞれの環境に合った形で生活の基盤を築いていました。
これは
-
黄河流域のように大規模な灌漑農業を中心にした大河文明
-
大草原を季節ごとに移動する遊牧社会
どちらとも少し違った独特のスタイルです。
騎馬軍はあったが「純粋な遊牧国家」ではない
高句麗には騎馬戦に優れた軍隊があったことが碑文や古墳壁画からわかります。

高句麗壁画の騎馬
See page for author, KOGL Type 1, via Wikimedia Commons
でもだからといって
-
「高句麗=典型的な騎馬遊牧帝国」
と考えるのは少し極端です。
実際には
-
生活の土台はあくまで定住と農耕にある
-
森林や山地、川を活かしながら狩猟も行う
-
そのうえで軍事面では騎馬を重視
という姿の方が現実に近いと考えられています。
王と有力氏族:五部制のイメージ
高句麗の内部構造を説明するときによく出てくるのが「五部制」という言葉です。
時期によって実態は変わりますが大まかには、
-
国の領域がいくつかの「部」に分かれている
-
それぞれの部には有力氏族がいる
-
その上に立って全体をまとめるのが王
というしくみになっています。
このイメージからわかるのは高句麗は一人の王が絶対的な力を振るう専制国家ではなく。複数の有力氏族との力関係のうえで成り立つ王権、だったとことです。
そのため、王位継承をめぐる争いや政権内部で派閥対立が絶えませんでした。それもこうした仕組みと切り離せません。
周囲の政権との関係:戦いと交渉のくり返し
高句麗の歴史はまわりの国々との関係なしには語れません。中国大陸側では漢・魏・晋・隋・唐といった大国があり、朝鮮半島側では百済や新羅が力を持っていました。
高句麗は
-
ときには中国側の国と激しく戦い
-
ときには使節を送り合って外交を進め
-
朝鮮半島の国とは同盟したり敵対したり
その時々の情勢に合わせて柔軟に立ち回っていました。
高句麗というと戦ってばかりというイメージを持つ人もいるかも知れませんが。外交的な交渉も活発に行う国でした。
周囲の政権との関係:戦いと交渉のくり返し
高句麗の文化を知るうえで欠かせない資料が、墳に描かれた壁画です。

高句麗壁画
[1], Public domain, via Wikimedia Commons
そこには、
-
宴の席で酒を酌み交わす人びと
-
楽器を奏でる楽人
-
狩りや行列に向かう騎馬
-
鳥や魚、さらには想像上の生き物が飛び交う様子
など、さまざまな場面が生き生きと描かれています。
これらの壁画からわかるのは、高句麗が武力だけを重視する国ではなく、音楽や宴、儀礼や信仰といった文化面も大切にしていた社会、だったということです。
人びとの暮らしの空気や、当時の価値観がそのまま絵の中に息づいているように感じられます。
漢文化の受容と在地文化の混ざり合い
高句麗の文化には、いくつかの性格が重なり合って存在していました。
一つは、
-
漢字の使用、
-
官職名や律令、儀礼といった制度、
など、中国の漢文化から取り入れた要素です。
そしてもう一つは、
-
狩猟文化、
-
山や川、動物などへの自然崇拝、
といった、この地域にもともと根づいていた文化です。
高句麗では
-
国を運営したり、公的な儀礼を整える場面では漢文化の知識を活用
-
ふだんの生活や信仰のレベルでは自然や精霊への古い信仰がそのまま続いている
という二重構造が見られます。
この「漢文化+在地文化」の絶妙な組み合わせは、のちに同じ地域で台頭する靺鞨・女真系の政権にも見られる特徴で、高句麗が様々な要素が入り混じった国だったことがわかります。
高句麗の滅亡とその後
唐・新羅との戦いと滅亡
長く東北アジアの有力政権として存在していた高句麗も7世紀に入ると内部の権力争いと外からの圧力が重なり、しだいに追い詰められていきます。
内部では、
-
王位継承をめぐる争い
-
有力氏族どうしの対立
といった不安要素が続きました。
一方で外部では唐が勢いを増し、朝鮮半島でも新羅が台頭してきます。
やがて新羅は唐と同盟を結び、百済・高句麗と敵対する立場になります。
この流れの中で
-
先に百済が滅び
-
続いて高句麗も唐の強い軍事的圧力に耐えきれず、
668年に滅亡しました。
高句麗の人びとの行方
高句麗が滅んだあと、その人びとがどのような道を歩んだのかについては、いくつかの流れが考えられます。
-
唐によって本国へ連行された人びと、
-
新羅の支配下に組み込まれた人びと、
-
旧領の周辺地域にとどまり、のちの渤海(渤海国)につながっていく勢力に合流した人びと、
など、それぞれが別々の運命を辿りました。
高句麗の滅亡が「完全な消滅」を意味したわけではなく、その文化や血筋はさまざまな地域で形を変えながら受け継がれていきました。王国としては幕を閉じても、人びとの生活や記憶はそのあとも続いていた、ということですね。
ドラマ『朱蒙』『風の国』と高句麗:どこまで史実?
ここからは、史実そのものではなくドラマが描く高句麗像についての話です。
ドラマが描く「古朝鮮→夫余→高句麗」は創作
ドラマ『朱蒙』では物語冒頭で「古朝鮮の滅亡」や「漢の支配」が強く描かれます。
そのため、
古朝鮮の失われた国を朱蒙が高句麗として再興した
というイメージができあがります。
でも、
-
歴史上の朱蒙伝承には「古朝鮮」という地名・国名は出てこない
-
扶余・初期高句麗の拠点とされる地域は平壌から離れている
という状況を踏まえると、
「古朝鮮→夫余→高句麗」
というのはドラマの作り話だとわかります。
ドラマは
-
視聴者に分かりやすい「壮大な物語」を提供する
-
そこに高句麗や扶余の伝承をうまくはめ込む
という方法でエンタメ作品としてのドラマの魅力を高めています。そのぶん、史実とはズレている部分があるのです。
山岳国家としての高句麗表現とロケ地
ドラマに登場する高句麗の風景は切り立った山々や霧に包まれた谷が多く、「山岳国家」という印象が強くなりがちです。
これは主に韓国国内の山地でロケを行っているからです。
史料や遺跡の位置から見える初期高句麗は満洲寄りの川沿いの地域に重心があり。山もあるが、農耕に適した土地も存在したと考えられます。
「これはドラマのビジュアル表現だな」
と割り切りながら楽しむことができます。
あくまでもドラマは作り話。史実とは違うということを覚えておきましょう。
関連記事
高句麗以前に栄えた古代王国の史実を紹介。
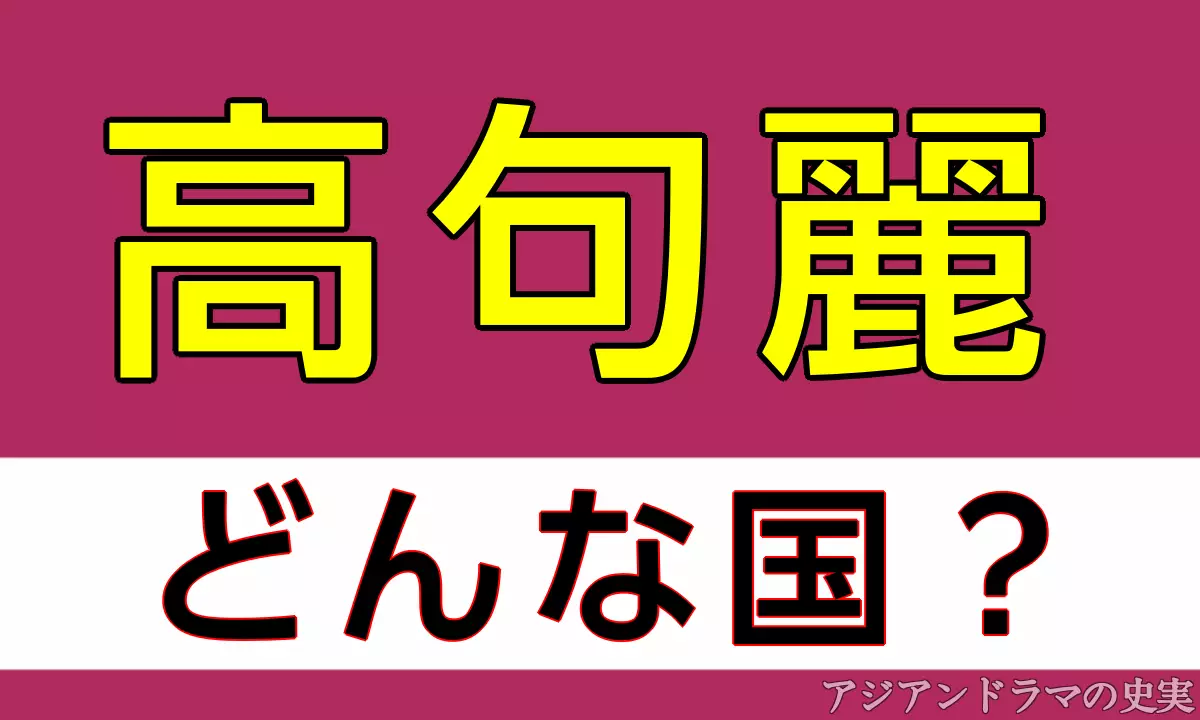

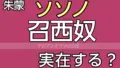
コメント