ドラマ『ケベク』で登場するキョギ王子は野心と未熟さを併せ持つ王子です。
史実の翹岐王子は日本書紀にわずかに記されるだけの謎の多い百済王子です。
でも史実の翹岐王子は政変の犠牲になり日本に渡ったと考えられる人物。ドラマと史実、二つのキョギ像を比較すると、百済王家の知られざる真実が浮かび上がります。
【この記事でわかること】
- ドラマ『ケベク』におけるキョギ王子の人物像とその運命
- 史実の扶餘翹岐(ふよ・きょうぎ)の生涯と日本書紀での記録
- 義慈王政権の変化と粛清の背景
- 「皇極元年」と「斉明元年」入れ替え説による年代矛盾の解消
- 百済末期の権力構造と王族の実像
ドラマ『ケベク』のキョギ王子
ドラマ『ケベク』で登場するキョギ(翹岐)王子は百済第30代・武王と王妃サテク妃(沙宅妃)との間に生まれた王子です。彼は義慈王(ウィジャ王子)の異母弟で、王位をめぐって兄と対立します。
母と祖父の強い影響下で育つ
キョギは幼い頃から母の強い影響下で育ちました。サテク妃や祖父サテク・チョクトクは権力を握るため、キョギを次の王に据えようと画策します。
キョギ自身も「王になりたい」という強い野心を持っています。
策士の母 vs 短慮な息子
でもサテク妃が冷静で思慮深い策士なのに対して、キョギは若く短慮で感情的です。母の計略を理解できず、先走った行動に出てしまうこともあります。
この“先走り”が彼の最大の弱点。やがて自らの首を絞めることになります。
兄ウィジャとの対立と焦り
兄のウィジャはだらしない王子を演じていたので、キョギはウィジャを見下していました。
でも成長したウィジャが手柄を立てるようになると、過剰に対抗心を燃やすようになります。
短慮な行動が招いた破滅的な結末
ドラマ後半では、キョギの行動が思わぬ失態を招いて王子の身分を剥奪されるという展開を迎えます。
「野心家ですが賢さが足りなかった男」。
それがドラマ版のキョギです。
彼の最期は自分の浅はかさ野心が招いた当然の結果と言えますね。
史実の翹岐(キョギ)王子
ドラマ『ケベク』に登場するキョギ王子のモデルが扶餘翹岐(ふよ・きょうぎ/プヨ・キョギ)です。
史実のキョギ=扶餘翹岐(ふよ・きょうぎ)とは?
| 項目 | 内容 |
| 氏名 |
扶餘翹岐(ふよ・きょうぎ)
|
| 生没年 | 不詳(? – ?) |
| 出身 |
百済王族
|
| 父 |
武王(百済第30代王)
|
| 母 |
不詳(史料なし)
沙宅王后説有り |
| 兄弟 |
義慈王(兄)、塞上(兄弟)、同母妹4人(『日本書紀』記述による)
|
史料の少ない王子
百済の王子ですが、『三国史記』など朝鮮半島側の史料には名前がなく。『日本書紀』にだけ登場します。
その理由は百済が唐・新羅に滅ぼされ記録が散り散りになった。『三国史記』は新羅側の視点で書かれていること。古代史においては王位に直接関係のない王子の扱いが低いこと、流罪や人質など不名誉な扱いの王族は正史に残すことがないことが挙げられます。
だから『三国史記』に名前がないからと言って存在しないわけではないのです。
父は武王
翹岐(キョギ)は百済第30代・武王の息子。第31代・義慈王の弟とされます。
ただ日本書紀には
弟王子兒翹岐
出典:日本書紀 卷第廿四 皇極天皇
とあり。弟王子の子・翹岐(=義慈王の甥)とも読めますが。翹岐にはすでに子もいるため、素直に義慈王の弟としておきましょう。
母は不明
翹岐の母は不明。
ドラマ「ケベク」ではキョギ王子の母はサテク王妃(沙宅王后)でした。でも沙宅王后が翹岐の母という史料はありません。
百済の政変で日本に亡命?
日本書紀によれば皇極元年に百済で政変が起きたことが書かれています。
去年十一月,大佐平智積卒。今年正月,國主母薨。又,弟王子兒翹岐及其母妹女子四人,内佐平岐味、有高名之人册餘,被放於嶋。
出典:日本書紀 卷第廿四 皇極天皇
(百済の使者が言うには)昨年11月に大佐平智積が亡くなり。今年の1月には百済王の母が崩御。弟王子の翹岐や同母妹の女子、内左平岐味、その他高官四十余りが島流しになった。」
皇極元年(642年)は義慈王が即位した次の年。この年にまず国王の母が亡くなりました。このとき國主母の地位にあったのは沙宅王后の可能性が高い。というのも沙宅王后は639年の弥勒寺建設まで生きてました。
639年の後に沙宅王后が亡くなり、その後新しい王妃が来たと考えるのは急過ぎますから。641年に武王が亡くなり、義慈王が即位したらそのまま沙宅王后が国主母になったでしょう。
沙宅王后の死とともに追放されたので、翹岐は沙宅王后の子ではないか?母の庇護が亡くなったので追放されたのではないか?というのです。
もちろん、その可能性もありますが。単に翹岐が反義慈王派の一員だったので島流しになっただけで、それだけでは沙宅王后の実の子かどうかはわかりません。
翹岐王子の日本での待遇
『日本書紀』では翹岐が倭国(日本)でどのような扱いを受けたかが記録されています。
皇極元年(642年)
旧暦2月24日。翹岐は呼ばれて安曇山背連の家に住まわされました。安曇山背連は百済との外交を担当する臣下です。
4月。大使 翹岐が従者を連れて天皇に謁見。
その後、彼は蘇我蝦夷の邸宅に招かれ親しく対談。蘇我蝦夷は鉄と良馬を贈りました。ただしこのとき塞上は呼びませんでした。塞上は義慈王の弟で、すでに倭に来ていた王子です。彼は素行が悪く義慈王が呼び戻そうとしていましたが、天皇は拒否していました。
もしかすると翹岐と塞上は仲が悪かったのでしょうか?
5月5日は、河内国で騎射(馬に乗って弓を射ること=軍事訓練)を見物。
島流しにあったとされていますが、日本でも立場は百済の大使。蘇我氏や朝廷の対応も他の王族並みに丁重に扱っています。むしろ義慈王の弟の塞上よりもいいくらいです。
権力争いに敗れた者が使者の名目で日本に送られることはあることですから。不思議ではありません。
翹岐の子と従者が死亡
5月21日には翹岐の従者、22日には子供が死亡しました。このとき翹岐と妻は我が子の喪は行いませんでした。というのも百済の習慣では父母兄弟姉妹夫婦でも喪は行わないというのです。
5月24日には妻子を連れて百済の大井の家(河内長野市大井)に移住。子は石川(河内国石川郡)に葬りました。
7月。朝廷で百済の使者・大左平智積をもてなす宴が行われ、翹岐も出席します。
なんと、ここで前年11月に死亡したはずの智積が登場します。
翹岐の眼の前で相撲が披露されました。これは日本最古の相撲記録の一つとされています。
智積たちは宴会が終わって退席、翹岐の家に行き拝礼しました。大左平といえば百済で一番偉い重臣です。翹岐はその大左平から丁重な挨拶を受ける立場にあったのです。
筑紫に再び到着
皇極2年(643年)
旧暦4月21日。筑紫の大宰府からの報告に「百済王の子・翹岐弟王子が使者と共に来た」とあります。
翹岐が百済使節の一員として来たことがわかります。
ここで問題なのが。昨年政変で追放されたのなら、なぜまたここで使節団のいち員として再来日しているのか?ということです。
百済王の子翹岐弟王子という言い方もややこしい。王の子なのか、弟なのかどちらなのでしょうか?ここでいう百済王とは先代の武王のことでしょうか?
翹岐が追放されたのは655年だった?
以上紹介したのが日本国内での通説です。でもこれには矛盾があります。
- 一度死んだ智積が再び登場する。
- 沙宅智積碑では智積は654年まで生きていることが確認されている。
- 追放されたはずの翹岐が日本と百済を行ったり来たりしている。
義慈王の即位直後に粛清はあったのか?
『三国史記』によると義慈王は即位当初は「恩赦を行い、民を視察し、善政を施した」とされます。粛清や暴政は一切記されていません。
義慈王が暴君と呼ばれるのは十数年後の655〜657年からです。何かの歯止めを失ったかのように突然乱れだすのです。
でもこの矛盾を解決する鍵があります。
それは日本書紀側の「皇極元年」と「斉明元年」の取り違えです。
というのも皇極天皇と斉明天皇は同一人物なのです。
つまり
皇極元年(642年)のこの部分
「去年十一月,大佐平智積卒。今年正月,國主母薨。又,弟王子兒翹岐及其母妹女子四人,内佐平岐味、有高名之人册餘,被放於嶋。」
これは斉明元年(655年)の出来事。それなら前年に智積が死亡しても問題ありません。
ここで「皇極元年」と「斉明元年」を入れ替えると次のようになります。
斉明元年説による再構成(年表)
- 642年 翹岐と沙宅智積が使節として来日。『日本書紀 皇極元年』
- 643年 翹岐が使節として来日。
- 654年 沙宅智積が死去『沙宅智積碑』 『日本書紀 皇極元年』
義慈王政権の転換期 - 655年 国主母(沙宅妃)死去。
豪華な建築・贅沢三昧
翹岐・岐味・高官40人ら追放 『日本書紀 皇極元年』 - 656年 成忠が諫言するも投獄・死亡 『三國史記・義慈王』
- 657年 王の庶子41人を佐平に任命 同上
- 660年 唐・新羅連合軍により百済滅亡 義慈王降伏
こうすることで
- 智積の「死亡→再登場」の矛盾が消える
- 義慈王の恩政期・暴政期が史実と一致する
- 翹岐が追放されたのに使節として何度も登場する不自然さが消える
と矛盾が一気に解決できるのです。
翹岐の立場から見た「政変」
翹岐の立場から見ると。兄・義慈王が即位してしばらくは平穏な時期が続きました。翹岐も外交団の代表として活躍したのでしょう。
しかし王は国主母(沙宅妃)と有力・臣下を失って行動がおかしくなりました。いえ、沙宅妃たちがいたから王の暴走が止められていたのかもしれません。
国主母と重臣を失った王は歯止めが効かなくなり、王族・高官を遠ざけていった。
その中で、翹岐は義慈王の暴走を止められなかったのでしょう。そればかりか「反王派」とみなされ同母妹たちと共に流罪に処されたのではないでしょうか?
『日本書紀』皇極元年の翹岐の記事はどこまでが使節として来たときのものか、亡命したときのものかはわかりません。混ざってしまっているのかもしれません。
島流しになった翹岐は倭に亡命したのか、別の島に流されたのかもわかりません。
まとめ:翹岐は暴君化した義慈王の被害者?
この記事で紹介したのはもし異本初期の「皇極元年」と「斉明元年」の記事がいれかわっていたのなら?という仮説です。
でもこの方が説明がつくと思うのですよね。
すると翹岐は暴君化した義慈王によって粛清された王子ということになります。
ドラマ「ケベク」のキョギとは全く違う人物ですよね。
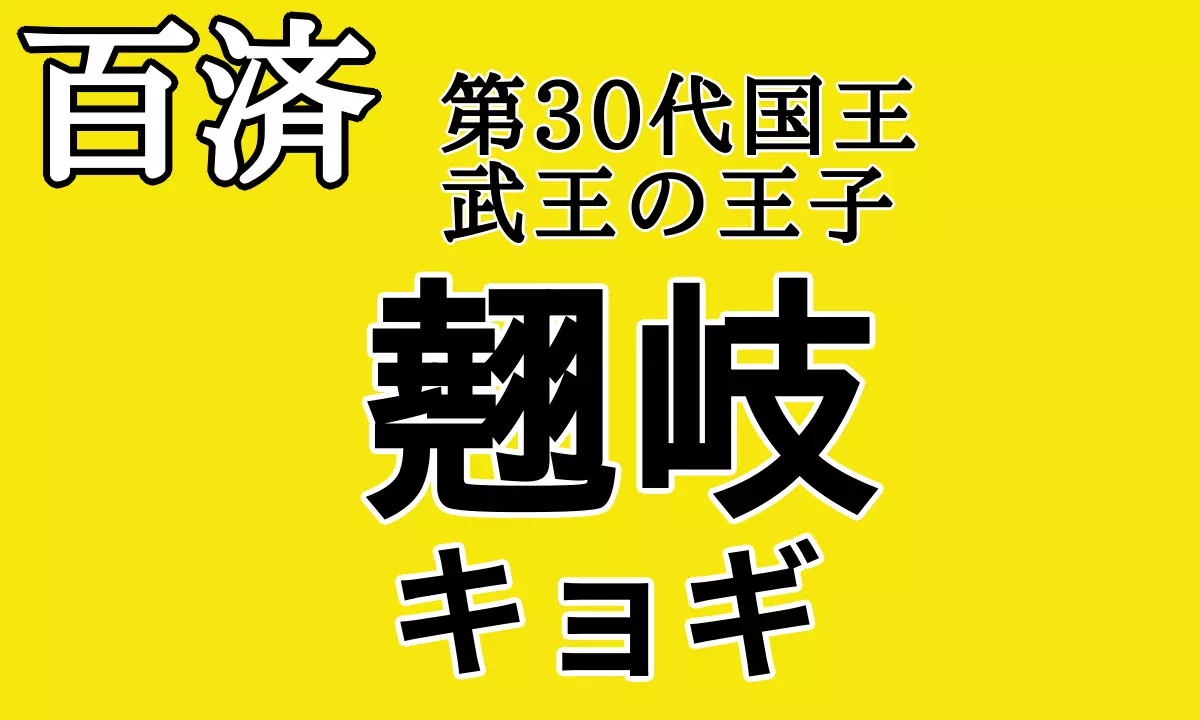


コメント