ヘモス将軍はドラマ『チュモン』で強烈な印象を残した人物ですよね。勇敢で民を守る英雄として描かれましたが、実際にそんな人物は存在したのでしょうか?
この記事では、史料に登場する「解慕漱(ヘモス)」を調査。ヘモス将軍が実在したかどうかを検証。
その結果。ヘモス将軍は実在の人物ではなく、高麗期の文献に登場する神話的存在「解慕漱」をもとに脚色された設定だとわかりました。文献に残る解慕漱とはどんな人物だったのか紹介します。
この記事でわかること
- ドラマ版ヘモス将軍と史料上の解慕漱の違い
- 解慕漱が初めて登場した史料と時代背景
- 夫余建国神話との関係
- 解慕漱=朱蒙の父説が生まれた理由
- ドラマでの脚色と神話的モチーフの関係
ドラマ『チュモン』のヘモス将軍とは?
ドラマ『朱豪(チュモン)』は高句麗建国を描いた時代劇。序盤で圧倒的な存在感を放ったのがチュモンの父・ヘモス将軍ですよね。あなたも「ヘモス将軍は本当に実在したの?」「史実ではどんな人物なの?」と気になったのではないでしょうか?
そこでこの記事ではドラマの設定と史料上の人物「解慕漱(ヘモス)」を比較しながら紹介します。
| 比較項目 | ドラマ『チュモン』のヘモス将軍 | 史料上の解慕漱(かいぼそう) |
|---|---|---|
| 登場時代 | 紀元前1世紀頃、漢帝国の支配下にある古朝鮮滅亡後の時代 | 前漢時代~北扶餘・高句麗建国神話の時代 |
| 立場・肩書き | タムル軍の将軍。チュモンの実の父。 | 天帝の子を名乗り、北扶餘を建国した神話上の王。 |
| 人物像 | 勇敢で誠実、民を守るために戦う理想的な指導者。 | 神の血を引く存在。五龍車に乗って天から降臨したと伝わる。 |
| 人間関係 | 恋人:ユファ。息子:チュモン。 | 柳花(河伯の娘)の前に光の化身として現れ、朱蒙の父となる。 |
| 目的・役割 | 失われた古朝鮮の再興と民族の自立を目指す。 | 天命により建国、王権の起源を象徴する存在。 |
| 結末 | 漢軍との戦いで致命傷を負い、柳花と別れた後に捕らわれる。 | 記録上の生涯は不明。神話の中で北扶餘建国の始祖として終わる。 |
| 史料的根拠 | ドラマの架空設定 | 『三国史記』『三国遺事』に登場。『好太王碑』『魏書』には記載なし。 |
| 実在の可能性 | 実在しない | 神話上の存在(後世の創作と考えられる) |
ドラマ版ヘモスは史実の人物ではなく、神話上の「解慕漱」を人間の将軍として脚色したもの。人間ドラマらしさを重視した設定なのですね。
ヘモスは実在した?主要史料を年代順に確認
ドラマで登場する「ヘモス将軍」ですが、歴史の資料を遡っても意外にも古代の記録には出てきません。『好太王碑』や『魏書』『隋書』など、高句麗や中国の古い史料には一切登場しないのです。
確認できる最初の出典は高麗時代の『三国史記』(1145年)。ここで初めて「解慕漱(ヘモス)」という名前が現れ、朱蒙の父として描かれました。このころから神話が整理され、人名をもつ父の姿が形づくられていったと考えられます。
史料を時代順に追ってみると、次のようになります。
① 好太王碑(414年)
高句麗の長寿王が建てた石碑。始祖・鄒牟(朱蒙)の父は「天帝」と記されるだけで、名前はありません。まだ神格的な存在として語られていたようです。
② 『論衡』など(前漢〜後漢期)
朱蒙そのものではありませんが、扶余や東明王の神話の元になったとみられる伝承です。北方民族的な太陽光の受胎など神話的モチーフが語られますが、ここでも解慕漱の名は確認できません。
③ 『魏書』(554年)・『隋書』(636年)
高句麗の起源を紹介する部分に太陽光で受胎など神話的な描写が残りますが、解慕漱は依然として登場しません。父を神として表現する点は変わりません。
④ 『旧唐書』(945年)
高句麗は扶余の別種と説明されるだけで解慕漱は不在です。
⑤ 『三国史記』(1145年)
ここで初めて解慕漱(ヘモス)が登場。天帝の子として朱蒙の父として設定されます。つまり、この書が最初に名前が登場した記録といえます。
⑥ 『三国遺事』(13世紀後期)
北扶余の建国神話に解慕漱がはっきりと位置づけられ、五龍車で天から降臨する王として描かれます。この時期になると、天帝を祖父、解慕漱を父とする関係も見られるようになります。
歴史の資料を比べてみましたが、古い5〜10世紀の史料に「解慕漱」という名は出てきません。
12世紀の『三国史記』で初めて登場。以後の高麗期の文献で物語的に整えられていったことが分かります。
つまりもともとは名前のない神話的な父(天帝)だったのが、後の時代に「ヘモス」という固有名を与えた存在です。
ドラマの「将軍ヘモス」は、後の時代に付け加えられた名をもとに人間的な父像として脚色した人物像といえるでしょう。
『三国遺事』の解慕漱
『三国遺事』は正史『三国史記』(1145)に収録されなかった伝承を集めた高麗期の文献で、北扶餘・高句麗の建国神話に解慕漱が登場する要資料のひとつです。以下に要点を簡潔に整理します。
- 北扶餘伝:天帝が五龍車で降臨し王となり、自らを解慕漱と名乗る。子は解扶婁。東明王の系譜へつながる。
- 高句麗伝:柳花が光を受けて懐妊し、一子(卵)を産む。父は天帝の子=解慕漱とされ、子は朱蒙。
| 項目 | 北扶餘伝 | 高句麗伝 |
|---|---|---|
| 解慕漱の位置づけ | 天帝そのもの(王) | 天帝の子(朱蒙の父) |
| 受胎モチーフ | — | 太陽光(光の到来) |
| 系譜の帰結 | 解扶婁→東明王へ連なる | 柳花+解慕漱→朱蒙 |
ポイント:同一文献内でも「天帝=解慕漱」か「天帝の子=解慕漱」かが揺れており、後の時代に編集された痕跡が読み取れます。これは「名指しの父=解慕漱」が高麗時代に付加・再編された可能性と考えられます。
夫余は解慕漱が作った国ではない
歴史上の夫余の建国者は解慕漱ではありません。東明王です。
1世紀後半の後漢時代に書かれた「論衡」では夫余の建国神話が載っています。
その内容を簡単に紹介すると。
橐離国(たくりくこく)の王が侍女を妊娠させた。王が侍女を殺そうとすると、侍女が鳥の卵のような霊気が降りてきて妊娠したと言ったので許した。侍女が子を産み「東明」と名付けられた。王は侍女に東明を育てさせた。東明は矢が得意だった。国の人々は東明を恐れ追放しようとした。東明は逃げて南に向かい、川を渡ろうとしたが橋がない。すると魚や鼈(スッポン)が橋を作って渡してくれた。川を渡った東明は夫余の地にやってきて王になった。
出典:「論衡」
というもの。
ここには解慕漱は登場しません。夫余を建国したのは解慕漱ではなく東明王です。
実は夫余建国神話は高句麗建国神話とストーリーが同じです。高句麗が後にできたので当然、高句麗が夫余神話を真似たことになります。
解慕漱は存在しなかった?!
古い時代の資料には解慕漱は出てきません。
高句麗建国の資料で最も古いのが414年に作られた高句麗の好太王碑。
好太王碑では建国者・鄒牟王(朱蒙)の父は天帝になってます。父親は天空の神様。こうなると朱蒙の実在も怪しいですがここではそれは考えません。
554年に完成した歴史書「魏書」と636年の「随書」では高麗の始祖・朱蒙は母が太陽の光に当たり卵を産み、卵から朱蒙が産まれた。と書かれています。「論衡」に載っている夫余の建国神話のアレンジです。
945年の旧唐書では高麗(高句麗)は扶余の別種とだけ書かれています。
つまり。
古い時代の資料には解慕漱は登場しません。
どうやら解慕漱は後の時代に誰かが付け足したようです。
補足:
ネット上では『桓檀古記』を根拠にヘモスを「実在の王」とする記述も見られます。でも桓檀古記は1979年に現代人が作成した偽書であり、史料的価値は認められていません。日本はもちろん、韓国の研究機関でも歴史資料としては採用されていません。
解慕漱はどこから来た?
解慕漱が登場するのは1145年に高麗で作られた「三国史記」と1200年代後半に書かれた「三国遺事」。そのころすでに高句麗も夫余も存在しません。
三国史記などでは「河伯の娘・柳花に声をかけたのは天帝の子を名乗る解慕漱。河伯の娘が太陽の光に当たって妊娠したと」というので。解慕漱は太陽神ではないかという説もあります。
解慕漱は天帝の子を名乗っていますし、神だったのかもしれません。光を操ることもできたのでしょう。「三国史記」「三国遺事」だけを読んでいたらそう考えるのも無理はありません。
でも「女性が太陽の光に当たって妊娠、その女性から王や始祖が生まれる」のは北方民族によくある神話です。
好太王碑を作った長寿王の時代には建国者・鄒牟王(朱蒙)の父は天帝でした。
その後、高句麗末期には建国者・高朱蒙の父は日の光になってます。
でも高句麗時代の建国神話に解慕漱はいません。いつの間にか解慕漱が朱蒙の父になっているのです。
つまり。
まず建国者・朱蒙は神の子という伝説があった。
太陽の光を浴びた女性から王が誕生する北方系民族の神話の影響があった。
その後で解慕漱が朱蒙の父になった。
と考えられます。
では、誰が解慕漱を朱蒙の父にしたのでしょうか?
解慕漱誕生に解氏の暗躍?
ここからは私の仮説になります。
朱蒙を解慕漱に結びつけたのは解氏かもしれません。
百済の貴族・解氏
解氏は百済で力を持っていた貴族。
百済の建国者・温祚王とともに建国に貢献して重臣になった人物に解婁(かい ろう)という人がいます。解婁は夫余出身。
温祚は朱蒙の子で高句麗から来たと言います。それとは別に夫余から移住した人が百済北部にいました。温祚の勢力と解婁の勢力が協力して百済を建国したようです。解氏は百済の政治を動かす有力な一族になりました。
解慕漱、解夫婁は解氏の祖先?
「三国史記」「三国遺事」など朝鮮半島側の資料では解慕漱、解夫婁は夫余の王族になってます。
「三国遺事」によれば解慕漱は北扶余の初代国王。
解夫婁は解慕漱の息子。上帝(天帝)の命令で北扶余から出て東扶余を建国しました。
解慕漱、解夫婁は解氏の祖先だったのかもしれません。
解氏は自分たちの祖先は夫余の王族だ。神の子だ。朱蒙の父だ。と主張していたのでしょう。
つまり「解氏は百済王家よりも由緒がある」といいたいのです。
王をすげ替える力を持っていた解氏
5世紀の百済、蓋鹵王の時代。首都・漢城は高句麗の長寿王で陥落。王族はほぼ壊滅。その後、蓋鹵王の息子・文周が熊津を都にして再興しました。
このころ高句麗からの亡命者が百済や新羅に来ています。高句麗は労役がきついので逃げる人がいました。百済ではそうした人たちも仲間にして国を立て直そうとしていました。
でも王家も朝廷も壊滅状態なので地方の豪族の力を借りないといけません。
熊津時代の百済で力を持ったのが解仇(かい きゅう)です。解仇は文周王を殺害。三斤王を即位させました。解氏は王家に対抗できるほどの力を持ちます。解仇はやりすぎて対立勢力によって討たれましたが解氏が有力一族なのは変わりません。
祖先を盛って名家をアピール?
百済王家の扶余氏は高句麗の建国者・朱蒙の子孫を名乗っていました。
解氏は王家に対抗して自分たちの祖先も夫余の由緒ある一族だと主張していたのでしょう。
解氏は夫余出身です。本当に夫余の王族だったかもしれません。夫余の東明王の姓名は分かりませんが、解氏だった可能性もゼロではありません。
夫余は高句麗に滅ぼされたので言ったもの勝ちです。
そうした逸話が百済滅亡後も残ってしまったのかもしれません。
また。百済や高句麗滅亡後に解氏の生き残りが新しい国で自分たちの地位を上げるために「解慕漱=朱蒙の父説」をでっちあげたのかもしれません。秦氏が始皇帝の子孫と言ってるの同じです。
つまり解慕漱が登場しないのが本来の高句麗神話。他の人達が勝手に解慕漱を付け加え、それが後世に残ってしまった。といえるのです。
テレビドラマの解慕漱
朱蒙 2006年、韓国MBC 演:ホ・ジュノ 役名:ヘモス
ドラマでは神ではなく人間。主人公チュモンの実の父親。
古朝鮮が漢に滅ぼされた後、漢と戦う将軍という設定。
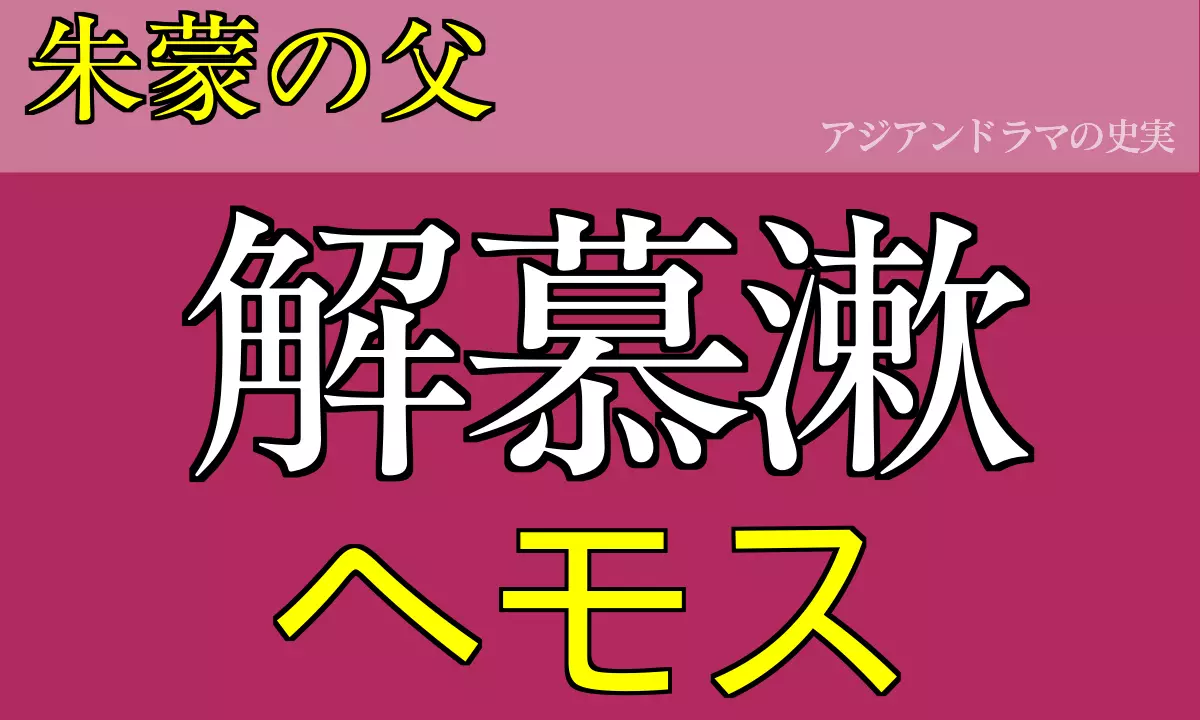


コメント