朝鮮王朝第14代国王である宣祖(ソンジョ)の治世に起こった日本との大規模な戦い壬辰・丁酉戦争(文禄・慶長の役)。この記事では建国以来最大の危機に直面した朝鮮国王・宣祖が開戦から終戦に至るまでどのような行動を取り、その立場と判断が戦局や後の朝鮮王朝にどのような影響を与えたのかを史実に基づいて詳細に追います。
この記事でわかること
- 壬辰・丁酉戦争の日本・朝鮮・中国それぞれの呼称に込められた意味合い。
- 開戦時の宣祖の即時避難と、暴徒化した民衆による王宮放火の事実。
- 宣祖が光海君を世子に指名した経緯と、「二つの朝廷」の役割。
- 明への依存を深めた宣祖の外交姿勢と、戦後の義勇兵・功臣冷遇の実態。
- これらの判断が光海君の失脚や後の清への服従につながった歴史的背景。
なお開戦までの経緯は宣祖(ソンジョ)とは?朝鮮王朝14代王の生涯をわかりやすく解説」で詳しく紹介しています。
壬辰戦争(文禄の役)での宣祖の行動
開戦と初戦の敗北(1592年4月)
1592年4月12日、対馬に集まっていた日本軍は海を渡り翌日、釜山が陥落しました。
4月16日早朝、王宮に釜山からの日本軍襲来の知らせが届きましたが、宣祖は機嫌が悪く大臣に会いませんでした。国王抜きで対策が話し合われ、宣祖が追認する形で決定が下されました。
- 李鎰を巡察使に任命し慶尚道へ派遣。
- 左議政・吏曹判書の柳成龍(ユ・ソンニョン)が総司令官となる。
- 柳成龍は女真族との戦いで功績をあげていた名将、申砬(シン・リプ)を呼び援軍の指揮を取らせる。
17日、宣祖から出陣命令を受けた申砬は、8000の兵を率いて日本軍迎撃に向かいましたが、27日、忠州で小西行長率いる1万8000の兵と戦い敗退。申砬は自害しました。
都からの避難と光海君の世子指名
28日、宣祖のもとに申砬戦死の報告が届き、宣祖は衝撃を受け、都から避難すると宣言しました。多くの大臣が反対する中、領議政の李山海が説得し避難が決定しました。現実問題として漢城は防御が弱く、兵たちも逃げ出しており、日本軍相手に戦うのは困難でした。
29日、宣祖は万が一に備え、大臣たちに迫られ、光海君(クァンヘグン)を世子に指名しました(ただし、この時点では明の承認を得ていない非公式な世子)。
宣祖はその日のうちに漢城を脱出。宣祖以下、王妃、側室、王子、大臣、侍女など100名近くが夜明けとともに出発しました。
【注釈】王宮を焼いたのは誰か
漢城を脱出した宣祖が目にしたのは、町から立ち上る煙と炎でした。住民たちの放火と略奪が始まっていました。奴婢から解放されたいと考えた人々が、奴婢の記録を焼くため王宮の書庫に火を放ち、王宮は朝鮮の人々や残された家臣らによって荒らされました。
つまり、王宮を焼いたのは日本軍ではなく暴徒になった朝鮮の民衆です。この事実は『朝鮮王朝実録』にも記されています。
開城から平壌への逃避行
30日、宣祖は夕方に開城(ケソン)に到着しました。開城では民衆が集まり非難したり泣き叫んだりして騒ぎとなり、宣祖自ら門に出て騒ぎを沈めようとしたほどでした。
5月4日、宣祖は漢城が日本軍に占領されたことを知ります。開戦してわずか21日後のことでした。宣祖は急いで開城を出発しました。
5月8日に平壌(ピョンヤン)に到着しました。

文禄の役 宣祖 避難経路
【補足】李舜臣の海戦初勝利
宣祖が平壌へ向かう途中の5月7日、李舜臣(イ・スンシン)率いる朝鮮水軍が日本水軍と戦い、朝鮮側の初めての勝利を収めました。朝鮮水軍の勝因は、船に大砲を載せて攻撃したことです。
亡命を考えた宣祖と「二つの朝廷」
宣祖は、漢城放棄を早すぎたと後悔し、兵を集め漢城奪回のため反撃を試みますが、5月18日の臨津江付近での戦いで金命元(キム・ミョンウォン)の朝鮮軍は敗退します。
開城も日本軍に占領され、宣祖は平壌を放棄し、寵愛する仁嬪金氏をつれて平安道・義州(ウィジュ)に避難しました。
このとき、宣祖は光海君を臨時の朝廷の代表にして国内を任せました。光海君たちは各地を回り義勇兵を集め抵抗活動を始めました。一方、宣祖自身は明の遼東に亡命しようとしましたが、大臣に説得され断念し、明に援軍を求めました。
明の援軍と反撃
6月15日、平壌が日本軍に占領されました。
7月16日、待ちに待った明の援軍が到着しましたが、平壌の日本軍への攻撃は敗退しました。
8月には女真族のヌルハチが明と朝鮮を支援すると申し出てきましたが、宣祖は「野蛮族の助けを受けるのは不名誉」として援助を断りました。
【注釈】日本軍を騙した休戦交渉
8月29日、明の沈惟敬(しん・いけい)と日本の小西行長の間で和議が成立し、50日間の休戦が決定しました。これは明側が本国から増援を送るための時間稼ぎでした。
12月、明から将軍・李如松(り・じょうしょう)率いる4万3千の精鋭部隊が到着。 1月6日、明軍4万、朝鮮軍1万が平壌の小西行長軍に攻撃をかけ、翌日、平壌を奪回しました。
しかし、このとき李如松の行った攻撃で朝鮮の民衆に大勢の犠牲が出ました。明軍が挙げた日本兵の首のうち、半分は朝鮮人の首を偽装したものだったともいわれています。
漢城攻防戦と和平交渉
戦線を広げすぎた日本軍は、朝鮮の厳しい寒さと食糧不足、病で消耗がひどくなりました。日本軍は朝鮮半島北部の部隊を漢城に集め、明軍を迎え撃つことになりました。
- 1月26日 碧蹄館の戦い:李如松率いる明軍と宇喜多秀家、小早川隆景率いる日本軍が戦い、明軍が敗退。李如松は戦意を失い和平を考え始めます。
- 2月12日 幸州山城の戦い:小西行長、石田三成ら率いる日本軍の攻撃を、権慄(クォン・ユル)率いる朝鮮軍が撃退。朝鮮軍勝利の報告が宣祖に届きました。
3月、明軍が日本軍の食料貯蔵庫を焼き払ったため、食料が不足していた日本軍は戦いは無理と判断し、和平に応じました。
【注釈】朝鮮不在で進む和平交渉
宣祖は和平に反対しましたが、明と朝鮮の関係では明に主導権があるため、宣祖の意見は無視されました。
4月18日、日本軍は漢城を出て釜山に撤退しました。宣祖は明軍に日本軍への攻撃を嘆願しましたが無視されました。
休戦期間中の活動
漢城が修復されると、宣祖は仁嬪金氏をつれて漢城に戻りました。光海君は引き続き各地で活動を続けました。
1594年3月、宣祖は朝鮮水軍に釜山の日本軍を攻撃するよう命令しましたが、明から和平交渉の邪魔になるため戦闘を行わないように命令されます。
1594年8月、宣祖は職務怠慢を理由に李舜臣を解雇し、元均(ウォン・ギュン)を水軍の司令に命じました。これは派閥争いの結果、水軍のトップが入れ替わったものです。
丁酉戦争(慶長の役)
再度の出兵と宣祖の避難
明の使節と日本の交渉が決裂し、1597年、豊臣秀吉は再び朝鮮への出兵を命令しました。二回目の出兵では、朝鮮半島の南にある全羅道・忠清道とその周辺を領地にすることを目指しました。
宣祖は明から新たな援軍を迎え入れ、10万の明軍とともに対応しました。しかし、全羅道・忠清道は日本軍に占領され、漢城にも迫る勢いとなったため、宣祖は再び重臣の進言を受け入れ、仁嬪金氏らをつれて避難しました。
豊臣秀吉の死亡と終戦
日本軍は占領地で城を作り、守りに入り、朝鮮・明軍との間で戦いが続きました。
1598年8月、豊臣秀吉が死亡し、日本と明の間で和平が成立し、日本軍は撤退をはじめました。
【注釈】日本軍の撤退と露梁海戦
和平が成立しているにもかかわらず、宣祖以下朝鮮と明軍は恨みを晴らすのはこの時ばかりと日本軍の撤退を妨害しました。
この戦い(露梁海戦など)で朝鮮・明・日本共に大きな被害が出ました。朝鮮軍では李舜臣や指揮官クラスの武将にも戦死者が続出しました。日本軍の撤退は11月には完了しました。
壬辰・丁酉戦争における宣祖の果たした役割
この戦いで宣祖の功績は、明に援軍を求めたことくらいでした。
- 戦前は日本を侮り、迎え撃つ準備をしていませんでした。
- 戦いが始まると早々と避難し、明に助けを求めました。
- 光海君は各地で義勇兵を鼓舞して人々の支持を集めましたが、宣祖は光海君を疎ましく思うようになりました。
明への過度な依存
朝鮮は明に助けを求めましたが、明軍の食料や兵士の相手をする女性は朝鮮が用意しました。また、明軍兵士による略奪や虐殺も起こり、朝鮮の民衆にとっては日本と明の両方が敵になってしまいました。
それでも宣祖にとって明は助けてくれた恩人であり、宣祖と大臣達は明の将軍・李如松を救国の恩人と称し、その死後、朝鮮国内で祀りました。
義勇兵・功臣への冷遇
義勇兵として戦った兵士は多くが賤民でしたが、戦いの間、光海君に官職を与えられた者もいます。しかし、戦争の後、宣祖は義勇兵に与えられた官職を剥奪し、賤民に戻しました。
戦いで功績を挙げた武将の多くが謀反の疑いをかけられて失脚しました。李舜臣も戦死しなければ謀反人にされたであろうといわれています。これは、生き残った者で宣祖以上に手柄を立てた者がいると困るという考えがあったからです。
この戦いの後、「日本に勝てたのは明のおかげ」「明を戦いに参加させたのは宣祖の功績」という理屈から、明に対する恩義・忠誠心はさらに強まります。
この考えが、やがて光海君の失脚と清への屈辱的な服従につながることになります。
壬辰倭乱・丁酉再乱の呼称が持つ意味
この戦争は、日本の学会では「文禄の役」「慶長の役」、一般には「朝鮮出兵」と呼び、豊臣秀吉時代の人々は「唐入り」と呼んでいました。
朝鮮・韓国での呼び方
李氏朝鮮時代の人々は壬辰倭乱・丁酉再乱といいました。
- 「壬辰」「丁酉」:年を干支で表現したもの。朝鮮は明から独自の元号の使用を禁止されていたため、干支で年を表現するしかありませんでした。
- 「倭」:日本の古い呼び方。従順という意味が含まれた日本の呼び方です。「倭」という字そのものには差別的な意味はないという意見もありますが、歴代の中国や朝鮮など中華思想の人々が蔑称として使っていたのは事実です。現代の中国人が「小日本」というのと同じです。古代の日本は漢字の意味をよく理解していませんでしたが、後に「倭」を「みやびではない」と考えるようになり、「大和」に改めました。
- 「乱」:秩序を乱すという意味。ここでいう秩序とは、中華の序列(中華の皇帝が世界一偉く、中国から離れるほど野蛮で卑しい)です。朝鮮から見て中国を上、日本を下の地位と考え、目下の日本が目上の朝鮮に起こした反乱という意味合いが込められています。
つまり壬辰倭乱は「壬辰の年に小さくて従順であるはずの日本が起こした反乱」という意味です。
差別的な表現であるため、現代の韓国の歴史学者の中には客観的な呼び方としてふさわしくないと考え、「壬辰戦争・丁酉戦争」と呼ぶ人もいます。しかし、自国中心主義的なマスコミや一般国民は「壬辰倭乱・丁酉再乱」と呼んでいます。
日本での呼び方
当時の日本側は「唐入り」と呼びました。豊臣秀吉にとっては「唐=明」を服従させるための戦いでした。大量の兵力を直接明に上陸させるのは困難なため、できるだけ海路を使わずに明にたどり着ける場所として朝鮮に上陸したのです。
現代では「文禄の役」「慶長の役」(文禄、慶長という年号の時代に起きた戦争)といい、一般には「朝鮮出兵」といいます。
中国での呼び方
中国での呼び方は特に決まっていませんが、中華思想そのままに「壬辰倭乱」と呼ぶこともあれば、「萬歴朝鮮之役」(萬歴:明の元号に起きた朝鮮での戦争)と呼ぶこともあります。
歴史を客観的に伝えるための呼称について
現在、最も中立的で客観的であるとして、日中韓の共同研究でも提唱されている呼称が、「壬辰戦争」です。これは、干支(えと)に基づいた中立的な時間軸と、「乱」(混乱や反乱)ではなく「戦争」という実態を表す言葉を用いるためです。
本記事ではこの国際戦争を客観的・多角的に捉えるため壬辰戦争の呼称を使っています。
【出典・参考文献】
※「壬辰戦争」の呼称提唱について:鄭杜熙・李璟珣 著、金文子・小幡倫裕 訳『壬辰戦争 : 16世紀日・朝・中の国際戦争』明石書店、2008年。
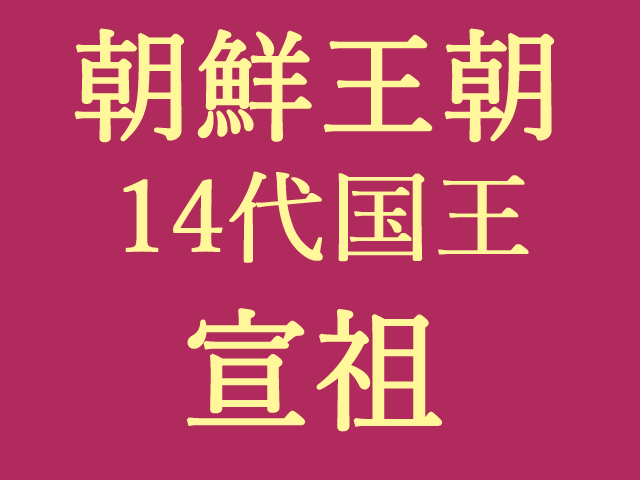
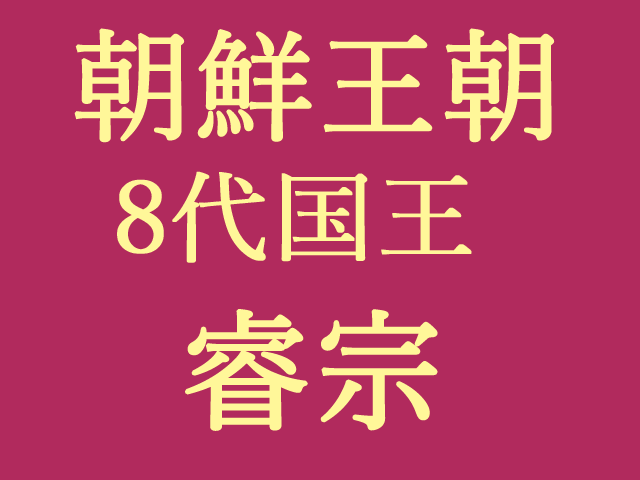
コメント