太祖・朱晃(しゅ・こう)は中国の五代十国時代の後梁の皇帝。
朱全忠(しゅ・ぜんちゅう)や 朱温(しゅ・おん)ともいいます。
唐末期に黄巣軍という反乱軍に参加。
唐に寝返って唐の権力を握り。
やがて唐で下剋上をおこして皇帝に即位。後梁を建国しました。
名前がいくつもあるのは
生まれた時から黄巣軍のときは 朱温(しゅ・おん)
唐では 朱全忠(しゅ・ぜんちゅう)
後梁建国後は 朱晃(しゅ・こう)と名乗ったからです。
裏切りを繰り返しているので中国では非常に評判が悪いです。
歴史書の内容をそのままドラマ化するとどうしようもない人物になってしまうのですが。滅茶苦茶な人生はドラマのネタになることもあります。
最近では、中国ドラマ「両世歓」の雍国皇帝・雍帝
「狼殿下」の煬王・楚馗のモデルにもなりました。
史実の後梁太祖・朱晃はどんな人物だったのか紹介します。
後梁太祖・朱全忠の史実
朱全忠はどんな人?
生年月日:852年
没年月日:912年
姓 :朱(しゅ)
名前:温(おん)→全忠(ぜんちゅう)→晃(こう)
国:唐→後梁
地位:後梁皇帝
廟号:太祖
父:朱誠
母:王氏
正室:賢妃張氏(元貞皇后)
側室多数
子供:7男5女、養子多数
主な子供
郴王 朱友裕
郢王(2代皇帝)朱友珪
均王(3代皇帝)朱友貞
彼は唐末期から五代十国時代の武将・皇帝です
日本では平安時代になります。
朱全忠と黄巣の乱
唐末期の852年。宋州碭山県(安徽省宿州市)でうまれました。
幼い頃の名前は朱温(しゅ・おん)
朱温は三男でした。
父は 朱誠。
儒学を教えている学者でした。
家は貧しく幼い頃に父が死亡。母や兄弟とともに、富豪の劉崇の家で小作人をしていました。
ところが朱温は畑仕事が嫌いで、乱暴者だったので村の人々からは嫌われていました。親戚の劉崇も朱温を嫌って朱温に何度も体罰を加えていました。でも劉崇の母は朱温をかわいがっていました。
黄巣の乱参加で頭角をあらわす
唐の僖宗の時代。山東では飢饉がおこり盗賊達が暴れまわっていました。
874年。塩の密売業者の黄巣(こう・そう)が仲間とともに反乱をおこしました。
877年。朱温は兄の朱存とともに黄巣軍に参加。
嶺南で戦った時、兄・朱存は戦死してしまいます。でも、朱温は手柄をたてて隊長になりました。
880年。黄巣軍が唐の都・長安を襲って占領。唐僖宗は成都に逃げました。その後。黄巣は夏州節度使(夏州方面軍)の諸葛爽を説得して味方につけました。
881年。黄巣は東南方面軍の司令に任命され鄧州(河南省鄧州市)を占領。その後も各地で戦い唐の反撃を阻止しました。
唐の節度使になった朱全忠
唐に降伏
882年。朱温は黄巣から同州の攻略を任されました。
ところが朱温は河中節度使(河中方面軍)の王重荣(おう・じゅうえい)と戦って敗退。黄巣に援軍養成しましたが、何度送っても援軍が来ません。
朱温の援軍要請は左軍使の孟楷に握りつぶされ黄巣には届かなかったのです。朱温は援軍がこないまま王重荣と何度も戦って破れました。
朱温は黄巣軍が各地で負けている、黄巣軍はもう長くはないという噂が黄巣軍内でも流れるようになりました。
信頼する部下の胡真と謝瞳は降伏するように進言してきます。そこで朱温は部下たちと相談。黄巣が派遣していた監軍使(見張り役)の厳実(げん・じつ)を殺害して部下をひきつれて王重荣に降伏しました。
唐僖宗はこの報告を聞いて「天からの贈りものだ」と言いました。
その後、朱温は唐軍と協力して長安から黄巣軍を排除。
手柄をたてた朱温は、左金吾衛大将軍、河中行営副招討使の地位を与えられました。さらに宣武軍節度使に昇進しました。
また皇帝に忠誠を誓う意味の「全忠」の名が与えられました。
李克用と対立する朱全忠
皇帝からの信頼を得た朱全忠は李克用(り・こくよう)と朝廷内の権力を巡って争いました。
李克用は中国風の名前を名乗っていますが突厥の沙陀族出身。戦いに強く、黄巣軍を追い詰めるのに実績をあげていた武将です。
朱全忠ははじめは李克用に下手に出ていましたが。李克用は朱全忠を見下していました。やがて朱全忠は李克用を酒に酔わせて暗殺しようとしますが失敗。
逃げた李克用は 朱全忠と猛烈に対立することになります。
でも李克用は戦いには強いのですが地方にいることが多かったので中央の権力争いからは脱落。むしろ地方で力を蓄えました。
朱全忠は長安にいて皇帝の直ぐ側に仕えていました。朝廷内でも宦官や重臣たちが権力争いをしていました。
日本の動き
唐の各地で反乱が起きて、長安も混乱していたこのころ。
日本では894年に菅原道真が遣唐使の廃止を進言しました。
すでに838年を最後に正式な遣唐使は派遣されなくなっていました(民間レベルの行き来はあった)。道真は唐の混乱ぶりを考えれば遣唐使そのものを廃止したほうがいいと判断しました。この後、遣唐使派遣は議論されなくなり事実上の廃止になります。
その13年後に唐は滅亡します。様々なルートから唐の動きはわりとくわしく日本に伝わっていましたし。菅原道真の判断も正しかったのです。
朱全忠が唐を滅亡させる
宦官を抹殺
宦官たちと争っていた宰相の崔胤(さい・いん)は朱全忠と手を組みました。
901年。それを知った宦官たちは皇帝を鳳翔に連れ去りました。
朱全忠は鳳翔を攻めて皇帝を取り戻し宦官を抹殺させました。宦官は唐王朝を悩まし続けましたが。
朱全忠は粛清という形であっさりと片付けてしまいます。ゴロツキあがりの朱全忠は容赦がないのです。
昭宗を殺害、哀帝を即位させる
ところが朱全忠が出陣している間に長安に残してきた甥の朱友倫がポロの最中に馬から落ちて死亡しました。
904年。朱全忠は甥の死は崔胤の仕業だと思い挙兵。崔胤を殺害しました。皇帝・昭宗を強制的に自分の本拠地の洛陽に移動させました。
朱友恭と氏叔琮に命令して昭宗を殺害。昭宗の子の哀帝を即位させました。哀帝はわずか12歳。朱全忠の操り人形です。
即位に向けて動き出す朱全忠
すでに朱全忠は皇帝になるつもりでした。哀帝を即位させたのはその準備です。
朱全忠のやり方に兄・朱全昱(しゅ ぜんいく)は「恩を仇で返す行為だ」と怒りました。
でも朱全忠は皇帝になるつもりなので今更止められません。朱全昱が一人で反対しても何も変わりません。
このころ期待していた長男の朱友裕が死亡。朱全忠は落胆します。
905年には唐の宰相・裴枢や、独孤損・崔遠たち高官30人あまりを左遷、任地に向かわせる途中で殺害して黄河に投げ込みました。
こうして反対勢力を始末するといよいよ皇帝になる準備の最終段階に入りました。もはや唐の官僚たちもすでに朱全忠のいいなりです。
唐滅亡
907年。朱全忠は哀帝から皇帝の座を奪いました。
唐は滅亡しました。大帝国だった唐も最後はあっけないものです。
でもこの時期の唐はすでに長安周辺しか支配していません。各地では節度使(地方方面軍)が独立して勝手に動いていました。
唐はローカルな小国家に落ちぶれていました。朱全忠がやらなくても誰かが唐を倒していたでしょう。
梁の皇帝 太祖 朱晃 誕生
907年。朱全忠は皇帝になりました。国号を「梁(後梁)」にしました。
名前を晃(こう)に変えました。廟号は太祖(死後に与えられた称号です)
908年。用済みになった哀帝を毒殺しました。
唐を倒して後梁を建国した朱晃でしたが中国全土を支配できたわけではありません。後梁の支配地域はこの程度です。それでも中原を支配しているので、他の小国よりは大きいです。

普との対立
各地には朱晃を快く思わない武将たちがいます。彼らは自分たちで「王」を名乗ったり、唐からもらった爵位を名乗って朱晃に対立しました。
唐の武将だった李克用もその一人です。
李克用は「普王」を名乗り後梁と激しく対立しました。
908年。李克用が死去。息子の李存勗(り・そんきょく)があとを継ぎました。
太祖・朱晃は李克用がいなくなったスキをついて普を攻めました。
ところが李存勗の普軍に敗北。後梁軍は壊滅的な被害を受けます。その後、後梁と普は対立を続けますが、しだいに普におされるようになります。
乱れた私生活
太祖・朱晃は女好きでした。
正妻の賢妃 張氏(元貞張皇后)が死去すると、ますますひどくなります。
各地の領地を治めさせていた息子たちの妻を都に住まわせて、手当たりしだいに手をだしていました。
特に博王 朱友文の妻の王氏は美人でした。
太祖・朱晃は王氏を大変気にって寵愛しました。
やがて不摂生な生活が災いしたのか太祖・朱晃は病に伏せるようになります。
後梁太祖の最後
912年。病気が重くなった太祖・朱晃は王氏の夫・博王 朱友文を太子にする準備をはじめました。それを知ったのが郢王朱友珪の妻・張氏でした。もともと郢王 朱友珪は素行が悪く父の朱晃からは嫌われていました。ますます父に不満を持つようになります。
太祖・朱晃は朱友珪を萊州刺史に移動させました。朱晃は左遷した者の多くを殺害していました。朱友珪は自分がやられると思ったのか、朱晃に不満を持つ将軍と協力して反乱を起こしました。
宮殿に朱友珪たちの兵がなだれ込んで来ると宮中の者たちは逃げ出しました。
寝たきりで看病を受けていた朱晃は誰が反乱をおこしたのか知りません。「反乱を起こしたのは誰か?」と聞くと朱友珪がやってきました。朱晃は「早く殺しておくべきだった」と後悔しました。でもすでに手遅れ。
朱晃は朱友珪に殺害されてしまいます。
享年61。
その後、朱友珪が2代皇帝になりました。
テレビドラマ
近年では朱晃をそのままドラマ化したものはありませんが。
いくつかのドラマでは朱晃をモデルにした人物が登場しています。
両世歓 2019年、中国 雍国皇帝・雍帝のモデル。 演:邵兵
狼殿下 2020年、中国 煬王・楚馗のモデル。 演:丁勇岱
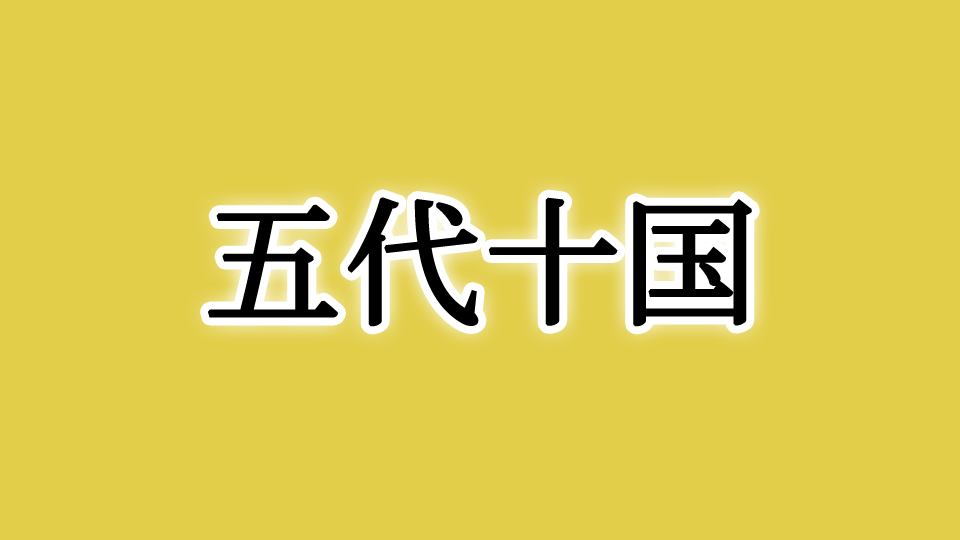
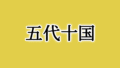
コメント