韓国時代劇に頻出する「大王大妃(てわんてび)」「王大妃(わんてび)」「大妃(てび)」のややこしい違いを解説。地位の定義、王の母とは限らない場合。位としての「大妃」の特別な役割についても、分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 大王大妃・王大妃・大妃の三つの位の明確な定義とランクの順番。
- ドラマで大妃が王の生母とは限らない複雑な継承パターン。
- 高麗時代からの王大妃という位が生まれた歴史的な背景と意味。
- 李氏朝鮮時代に3番目の地位として「大妃」が新設された特別なケース。
大王大妃(テワンテビ)
大王大妃(テワンテビ)はドラマでもよく聞く称号ですが、実はちょっと複雑なんですよね。
簡単に言えば「先先代の王の妃」のこと。多くの場合、今の王の祖母にあたる人になります。
ですが例外もあるんです。
王の弟が王位を継いだ場合なんかは新しい王の実の母が大王大妃になることもあります。だから「大王大妃=祖母」とは限らないと覚えておくと、ドラマが理解しやすいですよ。
「太皇太后」からのランクダウン
大王大妃という言葉もともとは古代中国の言葉から来ています。
先先代の皇帝の妻を意味する「太皇太后(たいこうたいごう)」が元になっているのです。
ここでポイントなのが、漢字を変えたこと。
「太」という字には「太上=これ以上はない=最高」という意味があります。ですが朝鮮は従属国としてワンランク下げて表現する必要がありました。
そこで、「最高」の「太」から、「おおいな=普通よりも偉い」という意味の「大」に変えたわけです。だから、このようにランクを下げた言葉に置き換えて使ったんですね。
太皇太后 → 大王大妃
また、年長者を尊敬する考えの強い朝鮮では大王大妃は王室でも最高の権威があるとされました。国王といえども、大王大妃の意見を蔑ろに扱うことは出来なかったのです。
歴代の大王大妃はたったの10人!その理由とは?
大王大妃は王の祖母にあたる人ですから、3代の王の時代を生き抜く必要があります。
27代続いた李氏朝鮮ですが、実は大王大妃になったのはたった10人しかいません。先代王の妃(王大妃)が生きてることはよくありますが、大王大妃は少ないですよね。それでも10人いたのは、いくつかの理由があるからなんです。
長生きしたからこそ!「人生50年」時代の偉業
いつの時代も女性は長生きですし、王の母は大切にされます。だから長生きする大妃はいました。
李氏朝鮮王朝の王の平均寿命は46.1歳、王妃の平均寿命は48.7歳でした。「人生50年」の時代です。60まで生きれば、それはもう長寿だったのですね。大王大妃になった人は全員この平均寿命より長く生きている人ばかりなんですよ。
仁粹大妃(インステビ)などは長生きした方として有名ですね。
親子の歳の差が鍵!王の晩年に王妃になったパターン
王妃が王より先に亡くなると次の王妃が選ばれます。この時、王の年齢に関係なく14~16歳の若い人が選ばれることが多かったのです。
「王と同じくらいの年齢でなければいけない」という考えは全くありません。だから親子ほど歳の離れた王妃が誕生することが珍しくありませんでした。
王の晩年に王妃になった人は当然、次の世代まで生きてることが多くなります。仁穆王后(インモクワンフ・宣祖の妃)、莊烈王后(チャンリョルワンフ、仁祖の妃)、仁元王后(イヌォンウォンワンフ、粛祖の妃)、貞純王后(チョンスンワンフ、英祖の妃)など、この理由で大王大妃になる人が多いですね。
幽閉生活の長かった仁穆王后以外は長寿です。大妃になると大事にされるし、王妃時代よりもストレスが少なく政争で命を落とすこともなくなるから長生きできるのかもしれませんね。
特殊な継承!王の母でも大王大妃になる場合
王位が兄から弟に引き継がれた場合、弟(新しい王)の実の母は大王大妃になります。この時、兄嫁(義理の姉)は王大妃という立場になるんですよ。
文定王后(ムンジョンワンフ)がこのパターンにあたります。ちょっとややこしいですよね。
後継者が短命だったパターン
王位を継いだ人が短命だった場合、前の王の妃(先代王妃)が存命している確率が高くなります。すると、あっという間に「先先代の王妃=大王大妃」になってしまうわけです。
そのパターンで大王大妃になったのが貞熹王后(チョンヒワンフ)です。彼女は李氏朝鮮初の大王大妃であり、垂簾政治を行った人としても知られています。
歴代の大王大妃
歴代の大王大妃をリストにしてみました。
()カッコ内の数字は享年(数え年)
| 慈聖大王大妃(貞熹王后)(66) 7代世祖の妃 9代成宗の祖母 王女の男ヒロイン・セリョンの母 |
| 慈淑大王大妃(昭恵王后・仁粹大妃)(68) 懿敬世子の妃 10代燕山君の祖母 懿敬世子は死後、徳宗の称号を送られました。 燕山君の祖母・仁粹大妃(インステビ)として有名 |
| 明懿大王大妃(安順王后)(55) 8代睿宗の妃 10代燕山君の義理の祖母(祖父の弟の妻) |
| 聖烈大王大妃(文定王后)(66) 11代中宗の妃 13代明宗の実の母。異母兄が王だったので、2つ前の王の妃ということで大王大妃になります。 オクニョに登場する大妃 |
| 明烈大王大妃(仁穆王后)(49) 14代宣祖の妃 16代仁祖の義理の祖母 華政の大妃、ジョンミョン公主の母 |
| 慈懿大王大妃(莊烈王后)(65) 16代仁祖の妃 18代顕宗の義理の祖母 19代粛宗の義理の曾祖母 宮廷残酷物語の莊烈王后の後の姿。張禧嬪が仕えた大妃。 |
| 恵順大王大妃(仁元王后)(71) 19代粛宗の妃 21代英祖の義理の母 トンイの最後の方に登場する王妃。 英祖にとっては義理の母だが、義理の姉が大妃となり、仁元王后は先々代の大妃になる。 |
| 睿順大王大妃(貞純王后)(61) 21代英祖の妃 23代純祖の義理の祖母 イ・サンの大妃。イサン亡きあと問題に |
| 明敬大王大妃(純元王后)(69) 23代純祖の妃 24代憲宗の祖母 25代哲宗の系譜上の母 |
| 孝裕大王大妃(神貞王后)(83) 孝明世子の妃 孝明世子は死後、文祖の称号を与えられました。 25代哲宗の系譜上の母 26代高宗の系譜上の母 |
大妃は、王妃時代とは別の名前で呼ばれることがあります。ドラマではわかりやすさを優先して、王妃時代の呼び方をそのまま使っていることが多いですよね。
例えば、ドラマ『オクニョ 運命の女(ひと)』に登場する文定大妃(ムンジョンテビ)の場合。
歴史の研究者は慈懿大王大妃(ジウィテワンテビ)と呼びます。でも一般には、王妃時代の文定王后(ムンジョンワンフ)という呼び方から文定大妃と呼ばれることも多いのです。
先先代なのに大王大妃にならなかった王大妃がいる
大王大妃は、基本的に「先先代の王の王妃」のこと。
でも先先代の王妃なのに大王大妃にならなかった大妃もいます。
中宗の母・慈順大妃(貞顕王后)の場合
その一人が、中宗(チュンジョン)の母である慈順大妃(ジャスンテビ。貞顕王后)です。
王位が暴君・燕山君(ヨンサングン)から、その弟である中宗に引き継がれました。中宗の母である慈順大妃は、先先代の王妃、つまり大王大妃になるはずですよね。
しかし、燕山君が廃位されたときに王妃も廃妃になったため、王大妃(燕山君の妃)がいません。そこで、中宗の母が王大妃になったのです。
王大妃(ワンテビ)の定義と豆知識
まずは王大妃の定義から。
王大妃(ワンテビ)は、「先代の王の妃」です。
普通は「今の王の母」になります。でも、王位が親から息子に継がれるとは限りません。
王大妃 ≠ 王の母
例えば、兄から弟に継がれた場合は、兄嫁が王大妃、実の母が大王大妃になります。
親戚が継いだ場合は、血縁関係が薄いのに王大妃になってしまうこともあります。
そう、大妃は「王の母」とは限らないのです。
ドラマに出てくるほとんどの大妃は、この王大妃にあたりますね。でもドラマでは省略して大妃と呼ばれることが多いです。
日本の皇太后との関係
現在の国家元首の母という意味では、日本で使う「皇太后」に近い意味があります。
『チャングム』が日本で放送されたときは、「王大妃」は「皇太后」に訳されました。
「大妃(テビ)」の二つの意味:まとめの呼び方と地位
大妃(テビ)という言葉は、実は二つの意味で使われています。
その1:大王大妃と王大妃を「まとめた呼び方」
大妃は、特に決まった地位を意味する言葉ではありませんでした。大王大妃と王大妃をまとめた言い方です。
ドラマではいちいち大王大妃、王大妃と区別せずに、単に「大妃様」と呼ぶことが多いですよね。
その2:地位としての「大妃」
しかし、大妃には地位としても呼び方もあります。
第24代の憲宗(ホンジョン)が亡くなったとき、なんと3世代の大妃が同時にいました。大勢いて紛らわしいので、区別する必要が出てきたのです。
そこで、王大妃よりワンランク低い呼び方として大妃という位を新設しました。
位のランク順
ランクとしてはこのような順番になります。
大王大妃 > 王大妃 > 大妃
これは「現在生きている歴代の妃の中でも3番目に偉い人」という意味です。この場合は、まとめた呼び方の大妃とは区別されます。
結論:困ったら「大妃」でOK
なんだかややこしいですよね。もう一度、簡単に整理してみましょう。
- 王大妃は、前の王様の妃。
- 大王大妃は、前の前の王様の妃。
- 大妃は、この二つをまとめた言い方(または3番目の地位)。
とりあえずドラマを見るときは、「大妃」と呼んでおけば間違いないです!
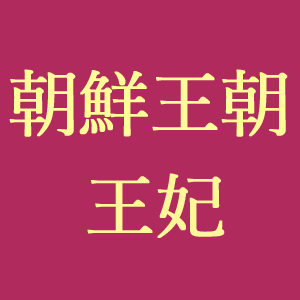
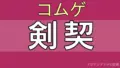
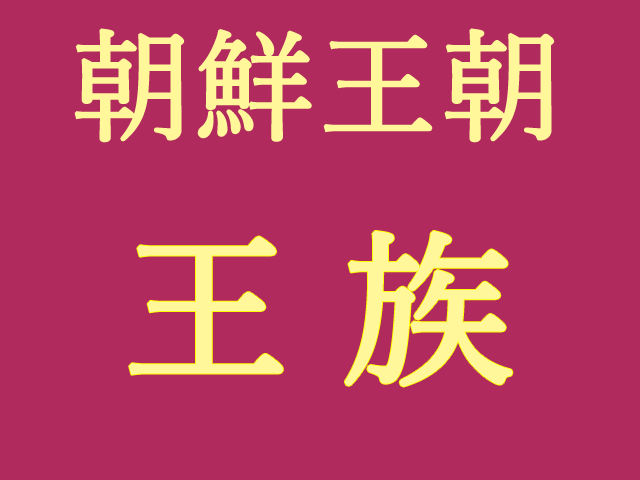
コメント