韓流時代劇「火の女神ジョンイ」は朝鮮史上初の沙器匠(サギジャン:宮廷陶工)という設定のユ・ジョンのお話です。
韓流ドラマ「火の女神ジョンイ」のモデルは百婆仙。豊臣秀吉の朝鮮出兵時に夫・深海宗伝とともに日本へ渡り、有田焼の基礎を築き「有田焼の母」と呼ばれました。朝鮮人陶工の波乱の生涯を紹介します。
この記事でわかること
- 「火の女神ジョンイ」の主人公ユ・ジョンのモデルとなった実在の人物、百婆仙(ペクパソン)の生涯。
- 夫・深海宗伝の日本での破格の待遇や、名前「深海」の由来となった謎。
- 百婆仙が有田焼の母と呼ばれるに至った背景。
- 有田焼の生みの親・金ヶ江三兵衛との関係。
ジョンイは架空?百婆仙は沙器匠ではない?
韓流ドラマ「火の女神ジョンイ」では主人公ユ・ジョンが朝鮮史上初の沙器匠(サギジャン)、すなわち宮廷陶工を目指す女性として描かれています。
でもドラマのモデルとされる百婆仙が実際に陶工だったかというと、その可能性は低いです。
陶工は夫・深海宗伝
史実として、陶磁器を作る陶工としての技を持っていたのはあくまで夫の深海宗伝でした。百婆仙は宗伝が亡くなった後にその家業を受け継ぎ、指導者として一族や弟子たちを束ね、有田への移住を決断し巨大な集団をまとめ上げた経営者・采配者としての役割を果たしたと考えられています。
「有田焼の母」といわれるのは彼女が実際にろくろを回したからではなく、一族と技術を海を越えた異国の地で存続・発展させた功績によるものなのですね。
儒教の教えが厳しかった当時の朝鮮で女性が公の職人(沙器匠)として名を挙げることはまずありえません。彼女は陶工たちの集団を率いた「お婆さん(百婆仙)」であり沙器匠はもちろん技術者としての陶工ですらなかった可能性が高いのです。
ドラマはほぼすべて作り話!
ドラマで描かれる、女性陶工ユ・ジョンの波乱に満ちた物語は残念ながらほぼすべて作り話だと思った方がいいです。ユ・ジョンは架空の存在です。
『ドラマと史実の比較』
史実と共通しているのは「朝鮮の陶芸に関わる人々が日本に来て日本の焼き物に貢献した」という、その事実だけ。百婆仙の朝鮮時代についての記録は一切残っていませんから、ドラマの内容を歴史的事実として混同しないよう注意が必要ですね。
ですが、その物語をきっかけに海を渡って日本の文化を支えた百婆仙という偉大な女性に光が当たったのは、非常に意義のあることではないでしょうか。
百婆仙(ペクパソン)の史実
まずは、百婆仙がどのような人物だったのか、その基本的な情報を見てみましょう。
百婆仙のプロフィール
- 生年:1561年
- 没年:1656年(明暦2年3月10日)
- 名前:不明
- 通称:百婆仙(ひゃくばあせん、ペクパソン)
- 夫:深海宗伝(ふかうみ そうてん)
- 子:平左衛門・宗海
彼女は朝鮮王朝(李氏朝鮮)の主に13代明宗の時代に生まれ、14代宣祖の時代に日本へ渡りました。日本では豊臣秀吉の時代にあたります。そして江戸時代の4代将軍家綱の時代まで生き抜きました。
朝鮮から日本へ連れてこられた経緯
百婆仙が日本に来たのは、文禄の役(いわゆる朝鮮出兵)のときです。彼女たちを連れてきたのは、後藤家信(ごとう いえのぶ)という人物でした。
後藤家信は現在の佐賀県武雄市にあたる肥前武雄の城主です。肥前国の戦国大名・龍造寺隆信の三男で、後藤家の養子となり家督を継ぎました。
家信は龍造寺家の家老・鍋島直茂とともに文禄・慶長の役(朝鮮出兵)に参戦しました。そして朝鮮から撤退する際、主君の命令で慶尚道金海から職人たちを連行します。そのときに連れてこられたのが夫である深海宗伝とその妻である百婆仙だったのです。
夫・深海宗伝(ふかうみ そうでん)の正体と優遇
百婆仙の夫、深海宗伝は朝鮮で陶工をしていた人物。日本に連れてこられた陶工たちのリーダー格でした。宗伝という名前は日本で付けられたもので、朝鮮での本名は伝わっていません。
ネット上では金泰道(キム・テド)という名が広まっていますが、これは違います。そもそもテドはドラマ終盤で亡くなっているので日本には着ていません。中にはドラマ「火の女神ジョンイ」でユ・ジョンの兄のような存在として登場するキム・テドが深海宗伝だと紹介しているサイトもありますが、誤解のもとはドラマの脚色にあるようですね。
宗伝の出身地とされる金海には金氏が多く住んでいて深海宗伝が金海金氏だった可能性はあります。もしかすると深海宗伝がキム・テドのモデルになったのかもしれませんが、ドラマの役名はあくまで架空のものなのです。
新太郎から宗伝へ
宗伝は日本に来た当初は新太郎と名乗っていました。彼は日本に来る前から従軍して朝鮮に渡っていた武雄広福寺の別宗和尚と行動を共にして親しくなります。そこで別宗和尚から「宗」の字をもらい、宗伝と名乗るようになったようです。
後藤家信による破格の待遇
日本に来て数年、広福寺の近くで暮らしていた宗伝は領主の後藤家信から内田村に土地をもらいます。一族とともに内田村に移り住み、陶磁器を作り始めました。
このとき、後藤家信は宗伝に姓を与えることにしました。出身地を尋ねたところ「シンカイ」と答えたので、「深海」になったといわれています。
『「シンカイ」の謎』
朝鮮南部の「金海」という地名を言ったのが日本人には「シンカイ」と聞こえたのではないか、というのが有力な説です。しかし韓国語では金海を「キメ」と発音するため、当時の朝鮮時代の発音が違ったのか、あるいは全く別の場所だったのか詳しいことはわかっていません。
当時の中国式発音では金海は「チンハイ」です。中国、朝鮮、モンゴルでは「カ行」と「ハ行」の発音、「チ」と「シ」の区別が曖昧になることがあったため、中国式発音の金海を日本人が聞くと「シンカイ」に聞こえる可能性も指摘されています。もしそうなら深海宗伝は中国にルーツを持つ人だった可能性すら出てきます。
当時、公に姓を名乗って良いのは特別な身分の人だけでした。後藤家信は深海宗伝を武士と同じ待遇にし、後藤家の被官(家臣)にしました。儒教思想の強い朝鮮では陶工が貴族階級の両班(ヤンバン)になることはまずありえませんから、これは破格の待遇です。それほど宗伝は重要な人物だと思われていたのですね。
江戸時代に入ると肥前国は佐賀藩鍋島家が治めますが、有田・武雄は引き続き後藤氏が領主を務めました。佐賀藩も朝鮮から来た陶工たちを手厚く保護しました。
有田焼の生みの親・金ヶ江三兵衛との出会い
一方、1616年。有田で金ヶ江 三兵衛が焼き物に適した土を見つけ、磁器の生産をはじめました。これが彼が「有田焼の生みの親」といわれる所以です。
金ヶ江三兵衛の素顔
金ヶ江 三兵衛の名も日本で名乗った名前です。朝鮮での名前は「李参平(り さんぺい)」といわれますが、明治になって創作された説もあり、朝鮮時代の名前は伝わっていません。ただし金ヶ江家には姓は「李」だったと伝えられているそうです。
彼は20代で陶工たちのリーダーになったため、両班だという説もありましたが、近年の調査の結果、両班ではなく賤民だったのかもしれないといわれています。儒教思想の強い朝鮮では体を使う職人の身分は低く、よほどでない限り両班ということはありえないのです。
金ヶ江 三兵衛は慶長の役(2回目の朝鮮出兵)の際、日本軍の道案内をしました。日本に協力したことで朝鮮に残れば報復される可能性があったため、撤退する鍋島軍に同行したといわれます。
武雄から有田へ
彼は武雄領の内田村ですでに多数の朝鮮人(深海宗伝たち)が焼き物をしていると聞き、合流しようとしました。しかし途中の板野川内(いたのがわち)で良い土を見つけたため、そこに定住したということです。
そして佐賀藩の時代になって有田でさらに良い土を見つけ、景徳鎮(けいとくちん)のような磁器を作り始めます。これが有田焼の始まりだといわれています。
ただ、この時代に有田で使われた登窯(のぼりがま)や唐臼(からうす)は、朝鮮にはありませんでした。そのため金ヶ江 三兵衛は明(みん)の人だった、あるいは明の技術を学んだ朝鮮人だったなどの説もあります。
「有田焼の母」百婆仙の移住と活躍
夫の死と決断
1618年(元和4年)、夫の宗伝が死去します。百婆仙は夫の跡を継ぎ、息子の平左衛門(宗海)とともに焼き物を続けました。
1629年(寛永六年)ごろまでには有田で磁器の生産が始まったという噂は武雄にも伝わったことでしょう。百婆仙は内田でも磁器を作ろうとしましたが、有田と違って武雄の土は柔らかすぎて磁器ができませんでした。
そこで百婆仙は領主を通じて佐賀藩に有田への移住を認めてもらうことにしました。
百婆仙、有田へ
1630年~1631年(寛永7~8年)ごろ。百婆仙はなんと一族と弟子960人を連れて有田の稗古場(ひえこば)に移住します。
他にも焼き物職人が続々と有田村や周辺の伊万里村に集まり、有田は焼き物の大生産地となりました。その噂を聞きつけ、陶工以外の日本人もやってきて窯を開くという賑わいぶりでした。自分の窯を持たなくてもレンタルの窯もあり、焼き物を作りやすい環境があったともいわれています。
日本人陶工の追放と保護政策
しかし、1637年(寛永14年)ごろから問題が起こります。焼き物を作る人が増えすぎたために、大量の薪が必要となり、山の木々が伐採されて荒れ果ててしまったのです。
そこで佐賀藩では、朝鮮人陶工とその子孫以外は焼き物をしてはいけないという決まりを作りました。由緒のある陶工を除いて、日本人陶工は有田や伊万里から追放されました。
この日本人陶工追放には、もう一つの目的がありました。それは、朝鮮人陶工を保護するためです。有田や伊万里で日本人陶工が続々と焼き物を生産すると、金ヶ江や深海の人たちの生活が脅かされるようになってきました。朝鮮人陶工の中には廃業する者も出ていたのです。
そこで、金ヶ江 三兵衛が佐賀藩に訴え出たのです。
佐賀藩としても、金ヶ江や深海の人々が作る高品質な磁器は重要な収入源であり、彼らの生活は保証しなければいけません。そこで、模倣品を追放することにしたのでした。
こうした佐賀藩の保護もあり、百婆仙率いる深海一族と、金ヶ江 三兵衛率いる金ヶ江の人々は、磁器の生産を続けました。百婆仙は多くの弟子を育て、ついに「有田焼きの母」といわれるまでになったのです。
百婆仙という愛称の由来
1656年(明暦2年3月10日)、百婆仙は96歳で亡くなりました。人生50年の時代ですから、当時としてもとても長生きしたことになります。そこで子孫たちは、「100歳(近く)まで生きたお婆さん」という意味で百婆仙という愛称で呼んだそうです。
深海宗伝と百婆仙の子孫、深海家はその後も有田焼の家として続き、苗字帯刀を許され、窯元として栄えました。明治維新で一時廃業したものの、明治時代になって復活。陶磁器製造販売をてがける深海商店として、現代でも続いているそうですよ。有田焼の始まりと発展は、朝鮮人陶工とその子孫たちによって支えられていたのですね。
海を渡った陶工たちと朝鮮の陶工事情
一方、朝鮮に残った陶工たちの多くは廃業し、技を受け継ぐ者はわずかとなりました。朝鮮の陶磁器は宋の陶磁器をもとに高麗時代に発展し、日本よりも進んだ技術を持っていました。
『職人冷遇の背景』
しかし李氏朝鮮時代になると職人たちは冷遇されました。儒教思想の強い朝鮮では体を使う仕事は卑しい仕事とされたからです。職人の身分は低く、賤民よりマシといった程度でした。賤民の職人もいたのです。
故郷で暮らしたけれど、低い身分のままでいつしか技も途絶えてしまった人。
異国の地につれてこられたけれど、高い身分を与えられ技を受け継いだ人。
どちらがいいとは言えませんが、歴史とは不思議なものですね。
百婆仙をモデルにしたテレビドラマ
「火の女神ジョンイ」 (2013)
演:ムン・グニョン
ユ・ジョンのモデルは百婆仙ではありますが、日本に来る前の百婆仙についてはほとんどわかっていません。朝鮮にも記録はありませんから、ドラマの内容はすべて作り話なんです。本当にわかっているのは「朝鮮の陶芸関係者が日本に来た」という部分だけなんですね。
ですが、ドラマとはそういうものなのです。ドラマをきっかけに、有田焼の発展に尽くした朝鮮出身の人たちがいたとわかるだけでも、素晴らしいことではないでしょうか。
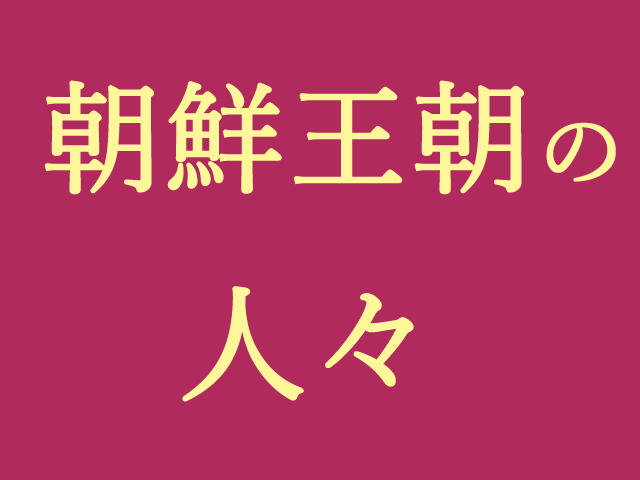



コメント
コロナ騒動後、2年前くらいから韓国バラエティを皮切りに、韓ドラにハマりました。
このドラマ、最後は倭国に渡ったとのことで、『もしかして?』と思って観ました。
九州人です! 有田の陶器市はコロナ騒動以前は、GWには、とても賑わうイベント。
通常時に行くと、とてものどかな趣きのある佇まいです。
有田焼が有名なのは、昔、有田港から陶磁器を西欧に出荷していたからだとか。
本当は??『伊万里』のほうが、鍋島藩用窯だったようで、、、大河内山という所に、
関所後が残っており、傍に朝鮮陶工達のお墓が沢山あるのです。
連行されたのか、自主的に来たのか、わからないけれど、
異国の地よりは、自分の国で死にたかったのでは無いか?と、もう20年以上前ですが、
感じました。ジョンイや、当時のサギジャン達の子孫かもしれませんね⁉︎
九州は観光地が多いので、佐賀は地味めですが、こういう陶磁器の歴史に興味ある方には、オススメの地です。百均でも、いろいろ買える時代になってしまったけど、
日常生活に、美のエッセンスを届けてくれた祖の存在は、理解し、感じていたいものです。
こんにちは。
400年前に日本に来た人たちの技術が受け継がれ発展して今では地元の名産品になっているのは素晴らしいですね。「ジョンイ」は作り話ですので百婆仙や深海宗伝がどういう人だったのかは謎ですけれど。日本に来た人一人ひとりにその人のドラマがあったのでしょうね。佐賀の陶磁器文化がこれからも発展するように願ってます。
有田焼の祖は「李参平」と習った世代です。「山川出版社詳説日本史」で調べてみると、「李参平」の名前そのものがありませんでした。(2010年出版)
念のために「山川出版社の佐賀県の歴史」で調べてみると、李参平が初めて磁器の製作に成功したとあり、年号は元和2年の1616年とありました。(1998年出版)
朝鮮から来た百婆仙の3行目
佐賀県武雄市にある備前武雄の城主は肥前武雄が正しいのではありませんか。
李参平については後世に作られた名前なので文献によっては出てこない場合があるようですね。現在「李参平」と呼ばれている人が存在したのは事実だったのでしょう。
有馬焼ではなくて 有田焼ですネ
ギャラリーペクパソン様。申し訳ありません。ご指摘ありがとうございます。